2023年09月30日
ビンの中の小さな世界

筆者が子供の頃に「カバヤ文庫」というものがあった。これは岡山の菓子メーカーである、「カバヤ食品」が出していた本のシリーズで、カバヤキャラメルの箱の中にある券と引き換えに、一冊貰えるという仕組みだった。つまり、販売促進のための景品だ。本の内容は子供向けのマンガや小説などで、とにかく種類がやたらと多かったのを覚えている。むろん、わが家にもその何冊かがあり、筆者などは同じ本を繰り返し読んだりしたものだ。
このうち筆者の記憶に刻まれている一冊が、『ビンの中の小鬼』という小説。これは『宝島』で知られる、かのロバート・ルイス・スティーヴンソンの原作を、ダイジェスト化したものだったね。ビンの中に住む小鬼は、何でも願いごとを叶えてくれるが、持ち主が死ぬまでに買った金額よりも安く他人に売らないと、最後は地獄に落ちてしまうという、子供向けにしてはちょっと恐ろしいストーリーで、いや~最後はハラハラさせられたっけ。そのせいか、筆者にはこの話が今でも強く印象に残っているのだ。
そして、そのせいでもう一つ心に植え付けられたのが、ビンの中への興味というか空想というか…。とにかく何か小さなビンの中に、もう一つ別の生きものの世界があるということに、筆者は憧れのようなものを抱いてしまったのだ。いかにも田舎の純朴な少年らしい話じゃないか。で、さっそく筆者はケチャップなどの空きビンを見つけては、中でいろんな昆虫を飼い始めたというわけ。むろんビンの中は狭かったが、当時は今みたいなアクリル製の飼育ケースなど手に入らなかったし、何よりやっぱりビンでなければならなかったのだ。
筆者がまず始めたのは、アリを飼うことだったなあ。彼らがそこで生きて行くためには、ベースとなる土地が必要だった。そのため筆者は庭の土をスコップで掘り、ビンの底に10センチほどの厚さの土地を作った。そして、捕まえて来た数匹のクロオオアリという大型のアリを中に放つと、何日かするうちに、彼らはちゃんと土中にトンネルを掘って暮らし始めたのだ。このときは嬉しかったね。何しろ透明なガラスのビンだから、彼らの巣穴を真横から観察するのにはちょうど良い。筆者はエサの砂糖を与えたりして、土の中に作られた小さな世界にさまざまな想像を膨らませながら、毎日眺めては楽しんでいた。
このときの失敗は、金属製のビンの蓋にあけた穴が大き過ぎたことだった。中の酸素が欠乏しないようにと、筆者はカナヅチで釘を叩いて、蓋に通気用の穴をいくつか開けておいたのだ。それは子供ながらの知恵だったが、まさかその穴から全員が〝大脱走〟するとは、思いもしなかったね。ある日覗いてみて、中がもぬけの殻だと知ったときには、筆者もガックリしたものだ。クッソー! まあアリの体の大きさと穴の大きさを、事前に比較検討しなかったのがマズかったのだが…。
こうなると、もう少し大きな昆虫を飼いたくなるもの。筆者が次に選んだのは、秋の虫の定番・コオロギだった。こいつは原っぱなどに行けば、いくらでも素手で捕まえられたが、重要だったのはオスじゃなきゃダメということ。と言っても別にオスだけが好きという変な趣味ではなく、単にメスは鳴かないからというのがその理由だった。筆者は、コオロギの鳴く声を聴きたかったのだ。オスとメスの見分け方は簡単で、背中の羽に渦巻きのような複雑な模様があるのがオス、シンプルでスッキリなのがメス。オスはあの羽を擦り合わせて、涼しげな音を生み出すのだ。またメスのお尻から、長い産卵管が出ているのも分かりやすい目印だったね。
捕まえて来た数匹のコオロギをビンの中に入れた筆者は、お袋からキュウリやナスの切れっ端をもらっては、エサとして与えていた。彼らはよくエサを食べ、暗くなると部屋の片隅で賑やかな歌声を響かせてくれた。子供にとっては、ヤッター!と叫びたいところだ。と、ここまでは順調だったのだが、気がつけばいつの間にか何だか様子がおかしい。コオロギの数が減り、残り一匹だけになっている。いったい何があったんだ…? 原因は彼らの共食いだった。後になって知ったのだが、コオロギもタンパク質を必要とするらしく、キュウリやナスばかり与えていると、彼らは共食いを始めるらしい。夢野久作の小説ではないが、まさに〝ビン詰めの地獄〟。まあ、イリコなんかをときどき与えておけば良かったのだが、アホな少年はそんなことにまるで無知だったからなあ。
オニグモを飼い始めたのは、中学生になってからだった。これは明らかに『ファーブル昆虫記』の影響で、ファーブル先生はクモに愛情を込めて実に細かく観察していた。その薫陶を受けた筆者のお気に入りが、精悍なたたずまいのオニグモだったというわけ。脚が短く重戦車のようにズングリした殺し屋は、ビンの中でとても強くてカッコ良く、筆者はさまざまな他の昆虫をエサとして与えては、その食いっぷりを楽しんでいた。と言うと何だかまるで変態少年のようだが、つまりはオニグモ対昆虫の戦いのドラマを見たかったのだ。言わば〝ビンの中のリング〟みたいな感じかな。たとえばオニグモ対アシナガバチ、オニグモ対カマキリなんてね。格闘技ファンならこの気持ち、きっと分かって貰えると思うが…。
こうした少年時代のビンの世界への憧れは、いまやすっかり形を変え、筆者の心の中に生き続けている。と言っても、ビンはビンでも焼酎のビンだけどね。やっぱり現在の筆者が、焼酎のビンを見るとつい惹かれてしまうのは、その中に魅惑の世界を感じるからかも知れないな。酒屋の棚には、さまざまな美しいラベルの焼酎のビンが、ズラリと肩を並べている。筆者はそれらを眺めるだけで、何やら心が弾むのを感じるのだ。そこには何かが生きている。そう、じっと見ているとそのビンの中には、一匹の小鬼が潜んでいるような気がしてくるから不思議なのだ。もっとも、この小鬼は人間を天国へと案内してくれる良いヤツだが…。
2023年08月31日
天真爛漫すぎる牧野富太郎

このところ筆者は久しぶりに、NHKの朝ドラを観ている。この前はたしか作曲家の古関裕而氏をモデルにした、2020年の『エール』だったから、今回は3年ぶりということになるなあ。あのときは夏に開催される東京オリンピックに向けて、1964年の前回大会の「オリンピックマーチ」を作曲した、古関氏にスポットライトが当たったのだ。もっとも、新型コロナのおかげで、主要キャストの志村けんが放送開始直前に亡くなるわ、感染拡大で撮影は中断するわ、おまけに当のオリンピックが翌年に延期されるわ、あれこれ災難続きだったのをよく覚えている。まあ、ドラマ自体はけっこう面白かったんだけど…。
今回の朝ドラは、筆者にとってそれ以来ということになる。で、この『らんまん』がまた意外に面白い。主人公は神木隆之介扮する槙野万太郎で、モデルとなったのは植物学者の牧野富太郎だ。牧野氏が高名な学者だということは筆者も知っていたが、その人物像や業績についてはこれまで知る機会がなかった。まあ、植物学などには興味もなかったし、せいぜいその道のエラい先生くらいの認識だったのでね。しかし、この朝ドラを観るようになってから、筆者は俄然この人に興味が湧いてきたというわけ。
むろんドラマは史実の完全コピーではなく、そこには様々な脚色もあるだろう。だが、個々のキャラクターの設定や細々としたエピソードは別として、主人公の生き方や物語の本筋は、牧野富太郎その人の人生が反映されているはずだ。そう思ってこのドラマを観ると、ずいぶん常人離れをした人物だったことが分かる。なにしろこの人、エリートではなく小学校を退学した後、独学で精進し植物学の世界に名を成したのだから恐れ入る。考えてみれば前述した古関裕而氏も、独学で高度な音楽技法を身に付けた人物。やっぱり天与の才能というものは、人間にとって最強の武器なんだな。
といっても牧野富太郎は、無一文のビンボー家庭に生まれたわけではない。実家は高知県佐川町の岸屋(ドラマでは峰屋)という造り酒屋で、言わば富太郎少年は裕福な商家の跡取り息子。なので、幼い頃から塾で読み書きはもちろん、漢学や洋学に英語も学んでいた。つまり、小学校の授業に飽き足らなくなって自主退学し、以後は独学の道に入ったということらしい。なんだかあの天才発明家、エジソンを思わせるような話だが、こうなると国語算数理科社会の万能型学校エリートよりも、独学でおのれの好きな道に打ち込む一芸型天才の方が、独自の世界を持っている分だけ強いのだな。
もっとも破天荒な道を歩く人は、それなりのダークな部分も抱えている。一旦は土佐で妻を持ちながら東京に出た富太郎は、彼女を離縁し別の女性(壽衛=ドラマでは寿恵子)と所帯を持ち、その間も実家から莫大な金銭的支援を受けていたのだ。ドラマはこの辺りを美しいラブストーリーに仕立てているが、はたから見れば身勝手なトンデモ野郎だったんだな。おかげで彼は好きな植物の研究に、一心不乱に打ち込めたというわけ。ただし、富太郎への支出が嵩んだ岸屋はついに経営が傾き、やがて別の酒造業者へと譲渡される運命に…。一人の天才を支えた陰には、実家の破産という悲劇があったのだ。ちなみに最終的に譲渡された先は、現在も続く司牡丹酒造という会社で、屋号は「黒金屋」。なんと、マンガ家・黒鉄ヒロシ氏の実家だというから驚いた。
しかし、『らんまん』でも描かれているように、牧野という人は東大の研究室に向かうときも、野山に植物採集に行くときも、決まってスーツに蝶ネクタイ姿というのが面白い。まあ研究室はいいとしても、野山で泥にまみれ草木の中に身を投じていれば、汚れはしないかとついこちらも心配になる。筆者だったら間違いなく、ヨレヨレの作業着を着るんだけどね。そこにはちゃんと理由があるようで、植物に対して敬意を払うという、この人なりの哲学があったようだ。いやはや変人というか、さすがは元は良いとこの坊ちゃんというか、この辺が常人の考えの及ばないところなのだろう。
そんな牧野富太郎のスゴい点は、研究室に閉じこもらず、積極的に各地に出向いて植物を採集し、生涯で40万点に及ぶ標本を作成したこと。他所から寄贈された植物もあったとは思うが、それにしても個人で40万点はオドロキだ。そうした中から新種を発見し、名前を付けて発表した数は1千を超えるという。さすがはわが国の植物学のパイオニア。これらの標本は氏の没後、東京都立大学に寄贈され、現在は「牧野標本館」に保管されているようだ。こうした学者としての業績と、無鉄砲とも思える純粋な生き方の、両方をあわせ持つのがこの人物の魅力なのかもしれないね。
だが、筆者のようなデザイン畑の人間から見て、なにより感心するのは、牧野自身が手がけた植物画の見事さだろうか。京都の筆職人の手になる絵筆で本人が描いたらしいが、とにかくその正確さや精緻さ、さらにはレイアウトの美しさと、どれをとっても完璧としか言いようがない。学者としての観察眼もさることながら、画家としての表現力や、グラフィックデザイナーとしてのセンスの良さには、筆者などただただ圧倒されるばかりだ。石版印刷で刷られたこれらの植物画はモノクロだが、彩色して額に収めれば、そのまま絵画として部屋に飾っても十分イケるはず。これらの植物画には、牧野富太郎という類い稀なる人物の、神髄が込められているような気がするなあ。
2023年07月31日
車社会のSAGAアリーナ

佐賀市に今年の5月13日に開業したのが、「SAGAアリーナ」という巨大な多目的アリーナ。4階建で最大収容人員8400人というから、佐賀県にしては思い切ってつくったものだ。さっそくアイスショーや、バスケットボールの試合などが行われたようだが、娯楽施設の少ない佐賀に、ようやく待望のハコモノが登場したってわけだ。ちなみにアリーナとは基本的に、客席に周囲をぐるりとかこまれた室内競技場を言い、東京の日本武道館などが分かりやすい例だろう。
問題はSAGAアリーナへのアクセスだ。どうやらこの施設には駐車場がないらしい。つまり、ここへ試合やコンサートなどを観に行くには、人々は電車かバスを利用するか、または誰かに送迎してもらうか、そうした方法を選ばざるを得ないようだ(近所に住んでて、歩いて行ける人は別だが)。しかし、はたしてコテコテの車社会の佐賀で、駐車場なしでこの施設がやって行けるのかどうか、老婆心ながら筆者はちと心配になる。
なにしろ佐賀といえば、日本でも指折りの車社会と言えるだろう。近所のコンビニに行くのにも、馴染みのラーメン屋へ行くのにも、さらには居酒屋へ行くのにだって、とにかくまずクルマなのだ。ブラリと歩いて何かを食べに行ったり、コンサートを観に行ったりという習慣が、現在の佐賀県民にはまるでない。まあ、公共交通網が絶望的に貧弱なのだから、仕方がないといえば仕方がないんだけどね。だが、そのせいで通りを走る車はやたらと多いものの、商店街はシャッターのオンパレード、歩道を歩く人影はほとんど皆無という悲しい状況になっている。車は点と点を結ぶ便利な道具だが、街を育てたりはしてくれないのだ。
それもこれも、公共交通網を地道に構築して来なかったツケなのだろう。おかげで、佐賀市の中心市街地はずいぶんとサビしい。いや佐賀市内だけではなく、全県がまずクルマありきになっている。そんな車社会に首までドップリ浸かった佐賀県民が、はたして電車やバスを利用して、わざわざあのアリーナまで行くのだろうか? 筆者はどうもそこが想像できない。なにしろ、佐賀駅からアリーナまでは徒歩で20分ほどかかるが、ふだん歩く習慣のない人にはずいぶん遠く感じるはずだ。またバスという方法もあるものの、よほどシャトルバスを増発しない限り、大人数の客を捌ききれないのではなかろうか。
だが本来、駅やバス停などからイベント会場まで歩くのは、けっこう楽しいことなのだ。行きは開催される試合やコンサートへの期待に胸を膨らませ、帰りはその興奮を胸に抱えたまま、途中の飲食店で仲間と一杯やって盛り上がる。イベントを楽しむとはそういうことで、会場までの道中で飲んだり食べたりお喋りしたり、それらを含めて一つのレクリエーションなのだ。結果として、会場周辺の商店街にも需要が生まれ、街が活性化するというわけ。東京など大都市のイベントは、基本そういう仕組みになっている。
筆者も東京に住んでいた頃は、神宮球場や東京ドーム、はたまた新橋演舞場に国立劇場など、さまざまなスポーツや演芸の会場に足を運んだものだ。むろんそこへ行くには、近場の駅やバス停から歩くのが当たり前。ほとんどの観客は、みなそうやって会場入りをする。もっとも、この道中の雰囲気がまた捨てがたいのだ。コンサートを観に行く前に、蕎麦屋に立ち寄ってちょっと腹ごしらえしたり、ソワソワしながらマックを立ち食いしたり。また、野球やプロレスなどを観た帰りには、友人たちと居酒屋で祝勝会や反省会の乾杯をしたり…。同じような期待や興奮を共有する人間たちが、同じ空間に集まることによって、街には一種独特な活気が生まれていたものだ。これは、車社会では考えられないことだろう。
こうしたスタイルが佐賀にも根付くようになれば、SAGAアリーナやその周辺が、ひょっとすると活性化する可能性もある。おそらく佐賀県が施設に駐車場を設けなかったのも、そうした狙いがあったからだろう。もともと車社会になる前の佐賀市は、佐賀駅から中心的繁華街の松原あたりまで、人々は歩いて行ったものだ。なにしろ松原神社の周辺には、映画館や多くの飲食店が集まっていた。なので、そこへ遊びに行く人々の数も多く、途中の駅前通りにもずいぶんと活気があった。誰もが歩くことなど、苦にしてはいなかったのだ。それがいつの間に、どうしてこうなった…?
SAGAアリーナには、イベント会場としてぜひ成功してほしいが、そのためには佐賀県民も、何が何でもクルマという意識から脱け出す必要がありそうだ。つまりもう一度、足を使って街を歩くことの楽しさを思い出すこと。また周辺の商店街も、積極的な投資を求められるだろう。なんたって、佐賀駅からアリーナまでの通りは、飲食店も少ないしちと魅力にも乏しい。やはり華やかさが必要なのだ。だが、知恵と工夫でやれば出来るはず。少し時間が掛かるだろうが官民一体で、ハコモノを中心とした街起こしの理想形を、この佐賀でぜひ見せてほしいものだ。
2023年06月30日
美味いものはいつ食べる?

最近は日本のフルーツサンドが外国人の間でも人気のようだが、この前見たYouTubeの動画では、各国の女性がイチゴサンドを食べる様子を映していた。まあ、どこの国でも若い女性は、こういうフンワリした甘いものが好きなんだな。面白かったのはその食べ方の違いで、人によってイチゴを先に食べてしまうタイプと、最後の楽しみに取っておくタイプと、二つに分かれるのが興味深かったね。これは国籍に関係なく、その人の性格によるものなのだろう。
筆者はもちろん、美味いものは最後に食べるタイプ。イチゴサンドはちと遠慮するとしても、栗羊羹の栗や天ぷら蕎麦の海老天は最後まで残しておいて、フィナーレにガブリと頂くのが好きなのだ。その方がしばらく美味さの余韻を楽しめるし、また食べたいという次へのモチベーションにも繋がるというもの。ケチ臭い食べ方と言われようが、筆者は子供の頃からこれが好きなのだから仕様がない。だいいち、先に美味いものを食べてしまうと、あとに楽しみが残らないと思うんだけどね。
思うに、先に美味いものを食べてしまうタイプは、子供の頃に比較的恵まれた家庭で生まれ、ケチ臭いことを考えなくても、次々と美味いものが出て来る環境に育ったのかも知れないな。つまり、イチゴサンドのイチゴを先に食べたら、残ったパンの部分は無理に食べなくても良いという考え方だ。ケチケチしなくても、美味いものはいくらでも出て来るとなれば、子供の頃から気っ風のいい食べ方が自然と身に付くのだろう。これはこれで悪くはないと思うが、美味い部分だけを食い散らかすような食べ方をすると、世間から親のしつけを問われることになりそうだ。
反対に最後まで美味いものを取っておくタイプは、良くいえば計画的、悪くいえばケチで貧乏臭いとなるのだろう。筆者などはこれにピッタリだが、まあ金持ちじゃない家庭に育った以上、自然とそうなったのも仕方がない。もっとも美味いものが最後に待っているのだから、フィナーレに向けて気分は盛り上がるし、結果として食べ方も計画的で丁寧になる。むろん、食べ残しなどはトンデモナイ。もし美味いものを最後まで取っておいて、いよいよのとき満腹で食べ残したとしたら、世間からはアホと笑われるだろうな。筆者などはそうならないよう、食べ方には気をつけている。
ただし、美味いものを先にという食べ方は、弱肉強食の自然界では理にかなっているようだ。なにしろマゴマゴしていると、美味いものをいつ競争相手に奪われるか分からない。その前に自分の胃袋に入れてしまうのが、サバイバルの絶対条件なのだろう。例えば、草原の王者ライオンはシマウマなどを倒したとき、いちばん先に大人のオスやメスが食らうのは内臓の部分だ。そこは柔らかく、ビタミンなどの栄養が豊富と来ている。つまり、彼らにとってはいちばんのご馳走なのだ。そして残された筋肉などにかじり付くのが、子供のライオンという順番になっているらしい。生存競争は厳しいねえ。こうなると筆者のようなケチ臭いタイプは、どうやら自然界では生き残って行けなさそうだ。
ちなみに人間にとって、焼肉屋で最高のご馳走はロースやヒレといった柔らかな肉の部分で、モツと呼ばれる内臓はそれより下という格付けになっている。つまりわれわれは筋肉が大好きで、本当は栄養価の高い内臓を格下扱いしているわけ。ライオンが聞いたら目を剥いてうなりそうな話だが、美味いものの定義は動物によって違うということか。そういえば、モツの中でも腸のことを「ホルモン」と呼ぶが、一説ではこの語源は大阪弁の「ほるもん」だという。あちらでは捨てることを「放(ほ)る」と言うが、つまり肉屋では牛や豚の腸はもともと捨てるものだったことから、その名が付いたという説だ。これもやっぱり、ライオンが聞いたら目を剥く話だろうな。もっとも、安くて美味いホルモンは筆者も嫌いではない。
しかし、美味いものを最後に食べるには、それまで誰にも奪われないという、前提条件が必要になる。兄弟が多い子供ならまわりは敵だらけだし、自然界の動物もまた同じはず。なので人間だったら一人っ子、動物だったら敵の来ない場所を知ってる生き物が、断然有利となるだろう。なにしろ最後に食べようと取っておいた肉を、その直前に横取りされたらたまったものじゃあない。その点、ヒョウなどは捕らえた獲物を木の上まで引っ張り上げ、そこで悠々と食べるという習性を持っている。高い木の上なら、ライオンやハイエナの横取りを気にせず、じっくり食事が出来るわけだ。高みの見物をしながらの食事は、きっと極上の味がすることだろうな。その気持ち、筆者にはよく分かる。
もっとも、美味いものを最後まで取っておいても、食べてみたらガッカリということもよくある。当て外れという奴だが、この場合はショックも大きい。大事に取っておいた天ぷら蕎麦の海老天が、いざ食べてみたら衣ばかりで中身がショボかったときなど、誰もが人間不信に陥ることだろう。こんなことなら最初に食べて、ショックを和らげときゃ良かったと…。なので、美味いものを最初に食べるか、最後に食べるかの判断は、自己責任ということにしておこう。
2023年05月31日
ヒバリよ、高く上がれ!

佐賀県の麦の生産量は、全国でも指折りのようだ。田植えが始まる前の今の季節、麦の収穫期を迎えた佐賀平野は、一面の枯草色に染まっている。なので農道などを散歩すると、これ以上はないほどの、長閑な景色にめぐり合えるのだ。いいねえ、この美しい風景。まるでミレーの『落穂拾い』のような広々とした平野に、空ではひっきりなしにヒバリがさえずり…。筆者はこの季節の農道を歩くたびに、心が癒される思いがするのだ。
しかし、そんなヒバリの声を聞いてふと空を見上げても、なかなかその姿を発見するのは難しい。声はすれども姿は見えず、だ。スズメやツバメなら、そこらにいくらでも飛んでいるのに、ヒバリよお前はどこにいる…? そう思って探した人も、彼らの姿を見つけたときには、ちょっとビックリするはずだ。なぜならヒバリは、とんでもなく高い空をホバリングしながら、声だけは大きくさえずり続けているのだから。そりゃあ、見えないのも無理はない。ヒバリを漢字で書くと「雲雀」だが、まさに名前の通り雲に隠れるようにして飛んでいるのだ。
とにかくヒバリで驚くのは、長時間高い空にとどまり鳴き続けること。実際のヒバリはスズメより少し大きい程度の小鳥なのに、どこにこんなエネルギーがあるのかと思うほどだ。もっとも、ヒバリの声はカラスなどと違って、可憐で耳障りがいい。まるで、小娘がお喋りしているようにも聞こえる。筆者がむかし読んだ太宰治の小説『乞食学生』は、主人公の小説家が井の頭公園の玉川上水の土手で、ヒバリの声を聞きながら見た夢の話だった。読んだのはずいぶん前なので、細かいストーリーは覚えていないが、うららかな川の土手であの声をのんびり聞いていたら、誰だってつい眠くなるのかも知れないな。
ただし、ヒバリの声を「小娘がお喋りしているよう」と筆者は書いたが、調べてみたらとんだ間違いだったことに気がついた。これは「ヒバリの高鳴き」と呼ばれるもので、さえずっているのは実はオス。つまりあの懸命のさえずりは、春の繁殖期にオスが縄張りを主張し、メスにアピールをしている行動なのだとか。なるほど、そこらのカラオケ親父のような、ただの喉自慢じゃなかったんだな。長時間上空でさえずり続けることを「揚げ雲雀」というらしいが、オスはその後ゆっくり降りて来て、また舞い上がる行動を繰り返すのだという。そのうち、そのカッコ良さに惹かれたメスが飛んできて、カップルが成立するんだとか。このあたりはヒバリも人間も、なんだかよく似ている。
それにしても高高度爆撃機じゃあるまいし、ヒバリはどうしてああも高い空まで、舞い上がる必要があるのだろうか? もうちょっと低い方が舞い上がるにも楽だし、声も地上に届きやすいだろうに、無理しやがってと筆者などはつい思ってしまう。だが、当然そこにはヒバリなりの理由があるのだろう。そもそも草原に巣を作り、草原でヒッソリと暮らすヒバリは、春の繁殖期だけ賑やかな声楽家になる。だが、ホームの草原には高い木がないため、外敵から身を守るためには、彼らの手の届かぬ高い空で歌を歌わねばならない…。どうやらそういうことらしい。だとすれば「揚げ雲雀」は、弱者のサバイバル戦術とも言えそうだ。
そんなヒバリの声は古来、春の風物詩として日本人に愛されて来た。なにしろ暖かく晴れた日に、草の上であの可憐な声を聞いていると、誰だって人生が楽しくなる。太宰治の『乞食学生』も、若さへの憧れがにじむ明るい小説だった。もっとも、万葉集には大伴家持の「うらうらに 照れる春日に ひばり上がり 心悲しも ひとりし思へば」という歌もある。うららかに晴れた春の空で、ヒバリが楽しげに歌っているのに、ひとり物思いにふけるオレの心は、なんか悲しいぜという意味だが、これなどは映画の「対位法」のように、明と暗を対比させた高等テクニックなのだろう。ここでもヒバリは明るさの象徴なのだ。
日本以外の国でもヒバリは、声の美しい「春告げ鳥」として愛されているようだ。ヒバリは英語でスカイラーク(skylark)というが、この言葉には他に「陽気に遊ぶ」と言う意味もあるという。高い空で陽気に歌うヒバリのイメージは、洋の東西を問わず似たようなものらしい。なので日本の歌人・大伴家持のように、英国の詩人たちもヒバリをモチーフにした詩をいくつも残している。やっぱり感性豊かな言葉のアーティストにとって、あの歌声は創造力を刺激するものなんだな。ちなみに外食チェーンの「すかいらーく」の社名は、創業地が東京の「ひばりが丘団地」だったことによるのだとか。ま、ただの豆知識だが…。
だが、多くの日本人にとってヒバリの歌といえば、昭和のレジェンド「美空ひばり」を、忘れるわけにはいかないはず。なんといっても彼女は、戦後日本に舞い降りた不世出の天才歌手だ。8歳のときに初舞台を踏み、11歳から少女歌手「美空ひばり」として活動し、メジャーデビュー後は歌手のほかに女優としても大活躍、長く芸能界に君臨し続けた。この人の存在を抜きにして、昭和史を語ることなど不可能なのだ。それにしても、「ひばり」という芸名はまさに彼女にピッタリ。これは、8歳の初舞台で名乗った「美空和枝」(本名・加藤和枝)の「美空」から、インスピレーションを受けたものに違いない。なんたってうららかな春の空には、ヒバリの声こそ相応しいからね。この命名のセンスは勲章ものだと思うが、どうだろう…?
2023年04月30日
蔦屋重三郎、待ってました!

聞くところによれば、NHKが2025年に放送する大河ドラマの概要が発表されたようだ。タイトルは『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~』で、主人公は「蔦重」こと蔦屋重三郎だという。蔦重といえば18世紀後半の江戸で敏腕をふるった、出版プロデューサーとして知られている。筆者はこういう企画を待っていた。NHKの大河ドラマが、ようやく江戸文化にスポットを当ててくれるのなら、諸手を挙げて歓迎したいね。
なにしろ最近の大河ドラマは、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康などが活躍する「戦国モノ」か、幕末から明治維新にかけての動乱を描いた「幕末モノ」の繰り返し。たぶん、ファンの多くは食傷気味だったはずで、筆者も今年の『どうする家康』は初回からパスしている。そりゃあ、毎度出てくる人物が被っているのだから、話がマンネリ気味になるのも当たり前だ。遅ればせながらそれに気づいたNHKは、2024年の大河ではついに「平安モノ」をやるらしい。
『光る君へ』と題されたこのドラマは、平安時代中期を舞台にした、あの紫式部が主人公の物語のようだ。まあ「平安モノ」も新味があって悪くはないと思うが、どうもこれは恋と嫉妬と陰謀が渦巻く、女性向け宮廷ドラマの匂いがするなあ。筆者はこの手のものが苦手で、実を言うと『源氏物語』もまだ読んだことがない。男も女も化粧をした平安貴族の世界は、想像しただけでも何となく居心地が悪いのだ。なので、たぶん間違いなく来年もパスすることになるだろうね。
そうなると、2年の空白期間をおいて登場する2025年の『蔦重』に、筆者の期待は高まるというものだ。なにしろ江戸の町人が主人公の大河ドラマなど、初めてではないだろうか。それだけでも画期的だが、何より嬉しいのは江戸の出版文化に光が当たること。とにかくこの18世紀後半は錦絵のほか、洒落本に狂歌本、黄表紙などといった大衆向けの娯楽本から、有名な杉田玄白らの『解体新書』といった学問書、実用書、文芸書のたぐいまで、実に多種多様な出版物が世に出た時代なのだ。そこには、きらめくようなタレントたちの存在があったはず。当時の江戸も現代の東京も、全国から集った才能が交差する場所にかわりはない。
蔦屋重三郎はその中で、鶴屋喜右衛門と並ぶ出版プロデューサーとして、大きな足跡を残した人物なのだ。もしもこの蔦重がいなかったら、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵も世に出なかっただろうし、人気作家・山東京伝のベストセラーや、大田南畝による狂歌ブームも生まれなかったかもしれない。また彼は、後にビッグネームとなる、若き曲亭馬琴や十返舎一九、葛飾北斎などの面倒も見ている。さらには平賀源内とも交流があるなど、蔦重の周辺は驚くほど多士済々だ。まるで「江戸文化の宝石箱や~!」じゃないか。いや、その求心力には感心する。
しかし、この時代は面白い。江戸で出版ビジネスが大盛況だった頃、上方でも上田秋成が筆者の好きな名作『雨月物語』を書いているし、伊勢松阪ではあの本居宣長が活躍している。秋成と宣長はたびたび論争などもしているのだ。蔦重は松阪に宣長を訪ねたこともあるようなので、東西文化の交流もきっと盛んだったことだろう。かつては江戸時代といえば、身分差別の厳しい暗黒時代だったと、学校などでも教わった記憶があるが、実際は違ったはずだ。識字率が高く、自由なユーモア精神にあふれ、知的好奇心旺盛な庶民がいなければ、こうした出版文化の隆盛はあり得ないもんな。
ところで誰もが心配するのは、「戦国モノ」や「幕末モノ」のような合戦シーンがない大河が、はたして盛り上がるのかと言うことだろう。まあ、その心配は筆者にもよく分かる。なにしろ舞台は、平和が続く江戸時代の中期だ。しかも、登場するのは言わば市井の文化人たち。「赤穂事件」や「め組の喧嘩」のような、派手な乱闘場面もありそうにない。なので、話の筋としてはたぶん若い蔦重の成長物語に、彼を取り巻く多士済々の人間たちが複雑にからむ、群像劇みたいな感じになるんじゃなかろうか。後半はそこに、幕府の権力者・松平定信による弾圧が襲いかかる、というような…。おお、それだけで何となく面白そうじゃないの。
調べてみると、蔦重は吉原遊廓の生まれ。若いうちに貸本屋を開業し、24歳で『吉原細見』というガイドブックの編集者に就任した、つまり〝吉原情報〟のプロフェッショナル。そこから版元となって出版業界に乗り出し、以後は浮世絵に狂歌本に黄表紙にと、時代の先端をゆくヒット作を次々と生み出している。この男、きっと庶民のニーズを読む目に長けた、一流のプロデューサーであり文化人だったのだろう。だが残念なことに脚気により、47歳の若さで寛政9年(1797)に死亡。ビタミンB1を早くから摂っていればと惜しまれるが、まあ今となっては詮ないこと。2025年に蘇る蔦重の活躍を、筆者も今から楽しみに待ちたい。
2023年03月31日
原点はG線上のアリア

音楽好きの人にはそれぞれ、自分の葬式で流してほしい曲があるはずだ。歌が好きな人なら、たとえばジョン・レノンの「イマジン」とか、秋川雅史の「千の風になって」とか、美空ひばりの「川の流れのように」などは、人気があるんじゃなかろうか。クラシックファンならフォーレの「レクイエム」や、ショパンの「別れの曲」なんかがきっと定番だろう。筆者だったら、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」を所望したいところだが、「ふざけんな!」とあとで陰口を叩かれそうだ。
筆者の友人の一人は、バッハの「G線上のアリア」が希望なのだと言う。これも葬式にはぴったりの曲だが、あまりに美しく切なすぎて、想像するだけでなんだか悲しくなる。どうせならもっと明るい曲の方が、湿っぽくなくていいと思うんだけどね。だいいちバッハのバロック音楽は、本人のイメージにも合わないような気がするのだ。筆者ならこういうタイプには、プロコル・ハルムの「青い影」をオススメしたい。なぜならロックの名曲「青い影」は、「G線上のアリア」と曲のイメージがそっくりだからだ。
比べて聴けば誰でも気がつくはずだが、二つの曲はロックとクラシックという違いこそあれ、本当によく似ている。それもそのはずで、実は「青い影」は「G線上のアリア」を下敷きにして作られた曲なのだ。つまり、コード進行に大きな影響を受けている。これはパクリとかいうレベルではなく、原曲に触発されリスペクトしながら、ロックの世界に創出したオマージュと言うべきだろう。まあこれ、音楽の世界ではよくある手法なのだ。なので「青い影」を評価する人間はいても、クサす人間は誰もいない。しかし葬式でこの曲が流れたら、きっとカッコ良いだろうなあ。
ところで、この「青い影」に影響を受けた日本のロックといえば、すぐに思い浮かぶのがBOROの「大阪で生まれた女」だ。これは本人以外に萩原健一や桑田佳祐、五木ひろしなど、多くの歌手がカバーしている名曲だが、これまた比べて聴けば「青い影」に酷似している。これをパクリと言う人もいるが、「大阪で生まれた女」を名曲たらしめているのは、素晴らしい歌詞のお陰だろう。18番まである歌詞は、全体で一つの長大な叙事詩になっていて、若い男と女の出会いから別れまでを歌っている。この歌詞が曲とよく合っていて泣かせるのだ。曲が「青い影」にそっくりなのは、やはり同じコード進行のせいだろうが、そこを自家薬籠中の物にするのもミュージシャンの腕というもの。バッハだって文句は言わないと思うけどね。
「青い影」を下敷きにした曲では、ユーミンの「ひこうき雲」や「翳りゆく部屋」も有名だ。これも比べて聴いてみれば、誰だって「ああ、そうか!」と気づくはず。というか、もともと教会音楽が好きだった彼女に、大きな衝撃を与えた曲が「青い影」だったのだ。ユーミンは後年、プロコル・ハルムと共演することになるが、きっとそのときは感慨無量だったことだろう。「『青い影』を聴かなかったら、今の私はなかった」と彼女は言っている。数々の名作を生み出した彼女の曲作りの原点にプロコル・ハルムがあり、そのまた原点にはバッハの存在があったというわけだ。どうりで「翳りゆく部屋」は教会音楽っぽい。
「青い影」に影響を受けた曲といえば、チューリップの「青春の影」もその一つだと言われている。そもそも曲のタイトルからして、先輩へのリスペクトが窺われるもの。財津和夫が歌う冒頭のメロディを聴くだけで、「青い影」のオルガンのイントロを連想するのは、筆者だけではないはずだ。両者のコード進行はほぼ同じのようで、テンポやリズムなどもよく似ている。それによく聴くと、「青春の影」の伴奏にはオルガンも使われており、やはり教会音楽っぽさをどこかに漂わせているのだ。財津和夫の優しく甘い歌声が、神父様のありがたいお説教に聞こえるのは、そのせいかも知れないな。
しかし、日本のミュージシャンに多大な影響を与えた、プロコル・ハルムの「青い影」の原曲が、実はバッハの「G線上のアリア」だったというところに、筆者は音楽の面白さを感じる。たぶん、クラシックの名曲に源流を持つポピュラー音楽は、探せばゴマンと出て来るだろう。だが、それは決して悪いことではないはず。何しろどんな作曲者も、必ず先達の影響を受けている。すべての創作はマネしたり触発されたりから始まるわけで、まあ丸パクリは論外として、あとはそれをどう独自に発展させるかなのだ。音楽とは、無数の支流を生み出す巨大な一つの川と考えれば、原曲とオマージュの関係も理解しやすい。だとすれば、人が自分の葬式に流したい音楽も、もっと多様でいいんじゃなかろうか…。
2023年03月03日
春の心は魚心

そろそろ春めいて来た昨今、何となく心が弾むのは筆者だけではないはずだ。野鳥たちは恋の季節を迎え、池や川の魚も元気に泳ぎだすのがこの時期なのだな。自然の多い佐賀平野で、やっぱりまず人々の目に入るのは、彼ら鳥と魚の活発さだろうか。もっとも、爬虫類も同時期に活動を開始するわけで、早目に穴から出て来たヘビが、寒さのあまり死んでるのをたまに見かけたりする。ヘビが何より苦手な筆者などは、散歩の途中でそんな死骸に出くわすと、ドヒャッと叫んで逃げるしかないのだが…。
そう言えば、松尾芭蕉の俳句に「行く春や鳥啼き魚の目は泪」という、有名な一句がある。「行く春」だから季節的には晩春なのだが、筆者が中学生の頃から気になっていたのが、最後の「魚の目は泪」という部分。なんで魚が目に涙を浮かべるの?と、アホな子供だった筆者はずっと疑問を感じていた。なんたって、水の中にいる魚の涙なんか、人間に見えるはずがない…、というより魚が泣くもんかってね。芭蕉というおっさんもずいぶんデタラメを言うものだ、と長年思っていたのだ。
だが、大人になって『奥の細道』を読んだ筆者は、この句にある二重の意味を知って、アッと驚いたというわけ。これは、みちのくへの旅に出る芭蕉が門人との別れを惜しんで詠んだもので、「行く春や」は去り行く春への惜別を、「鳥啼き」は送ってくれる門人たちの泣く声を意味するのだとか。で、最後の「魚の目は泪」は、魚問屋の息子で芭蕉の支援者だった、杉山杉風の涙を意味するらしい。なるほどこれなら筆者の目にも、当時の別れの様子が浮かんで来るというものだ。東北新幹線などない時代、はるか遠いみちのくへの徒歩の旅は、永久の別れを覚悟しなければならない。こんな短い一句に、別れの情感をみごとに盛り込んだ芭蕉は、やっぱりただのおっさんじゃなかったんだな。
魚といえば、筆者にも思い出がある。と言っても、かつて熱帯魚を飼っていた思い出だけどね。けっこう大きめのアクリル水槽に、筆者はグッピーやネオンテトラやコリドラスといった、比較的安価な魚たちを入れて飼育していたのだ。なにしろ熱帯魚は、ヘタをするとすぐに死んでしまう。なので、初心者には安価な魚が無難なのだ。もちろん水槽にはヒーターや濾過用フィルター、また循環用ポンプや照明器具なども必要になる。思えばけっこう維持管理に手間がかかるペットだが、犬やネコや小鳥などに比べれば静かだし、二、三日放っといてもどうということもないし、楽といえば楽だったね。ただし、あの四六時中ブクブクというポンプの泡の音が、気になるっちゃあ気になったけど…。
水槽で熱帯魚を飼うなによりのメリットは、仕事に疲れたときの癒し効果だろうか。なんといっても、そこは水中の別天地なのだ。砂の上に置いた石や水草の間を、スイスイ泳ぎ回る熱帯魚をじっと見ていると、なんだか自分までその中で遊んでいるようで、安らかな気分に浸れるのが良かった。おまけに熱帯魚の中でもグッピーは、「卵胎生」といってお腹の中で卵を孵化させ、稚魚を出産するという変わった魚。メスのお腹が大きくなったと思ったら、気がつけば水槽の中に、小さなグッピーの子供が何匹も泳いでたり、ということがよくあった。ちなみにグッピーでヒレが大きく美しいのはオスで、メスは色気のないでかいメダカといった感じだ。
グッピーはそんな魚なので、放っといてもどんどん増えて行く。それはまあ良いのだが、せっかく色や模様のキレイなオスを買って来ても、知らないうちに素性の知れないメスと交雑して、あまり見た目がパッとしない子供が出来たりする。何だ、コイツは?なんてね。なので、キレイな血筋を守ろうとすれば、しっかり囲って管理する必要がある。このあたりは、歌舞伎界の御曹司が変な女に手を出さないよう、親が目を光らせるようなものだろうか。やっぱり人間も魚も、似たところがあるんだな。
ずっと以前の筆者がまだ学生だった頃の話だが、アルバイトで行かされた先が、千葉市内のとある工事現場。そこは同市でも有名なソープランド街で、道の両側には目も眩むような店々が立ち並んでいた。そんなものには目もくれず、マジメに働いていた筆者だったが、ふと脇を流れる小川に目をやると、そこには見たこともない色も鮮やかな小魚が、群れをなして泳いでいたっけ。誰もが驚いて指差していたのを、筆者はよく覚えている。後から気づいたのだが、あれは間違いなくグッピーだったな。ソープ店から流れ出た温水が川に入り、きっとグッピーの繁殖に適した環境を作ったのだろう。ソープ嬢と同じく、グッピーも生命力が強いのだ。その後、あの川で彼らの子孫がどうなったのか、ちょっとだけ筆者は気になるのだが…。
しかし、熱帯魚の飼育もいつかは終わるときが来る。奴らは値段のわりに、すぐに死んでしまうのが難点なのだ。で、主人のいなくなった水槽に次に入れたのが、ヒメダカという黄色っぽいメダカだった。これは安かったね。安いはずで同じ熱帯魚店でも、肉食魚のエサとして販売していた魚だ。ただし、飼育しやすくそこそこキレイな上に、熱帯魚みたいに簡単に死なない丈夫さがあった。おまけにエサやりを忘れていても、どうということはない。奴らは水草にどんどん卵を産み付け、いつの間にか自分でそれを食べてしまうのだ。なので増えもせず減りもせず、常に一定数を保って生きていた。そこが、ズボラな筆者には相性が良かったね。
こうして飼っていた魚と人が別れる機会は、たいてい引越しのときに訪れる。筆者もその後、都内某所に引っ越したおりに、ヒメダカも水槽も処分してしまった。犬やネコや小鳥などと違い、相手は魚なので変な感傷もなくバイバイしたわけだが、今でも別に魚は嫌いではない。先日たまたま寄った白石町の道の駅では、地元産の野菜や食品などに混じって、ガラス瓶に入れたメダカを売っていたっけ。瓶の中には何匹かのメダカが泳いでおり、筆者的には少しだけ懐かしい記憶がよみがえったが、買うことはしなかった。でもこのごろときどき、またちょっと覗いてみたい誘惑に駆られるのだ。なんでだろうな…。
2023年01月31日
緑の芝生は元気の素

この時期に公園などを歩くと、広い原っぱが枯芝になっているのをよく目にする。冬枯れして茶色になった一面の芝生は、見ているだけで寒々しい。筆者など、この原っぱが緑に覆われるのはいつの日かと、歩きながら想像したりするが、それもまた楽しいものだ。なにしろ、春の訪れを告げる青々とした芝生は、美しいだけではなく、人の心を元気にもしてくれる。言ってみれば、生命力の象徴でもあるんだな。
そうなると、日本のサッカーシーズンもいよいよ始まりで、今年も青い芝生の上で躍動する、サガン鳥栖の選手たちの姿が楽しみだ──。てなことを言うと、お前は公園の芝生とサッカー場の芝生を混同している、とどこからかヤジが飛んで来そうだ。いや、ごもっとも。Jリーグが始まって以来、日本のサッカー場の芝生は著しく改善され、一年中青々とした色にキープされている。つまり今や冬に枯芝になるサッカー場など、よほど田舎に行かなければお目にかかれないはずなのだ。
ところがどっこいお若えの、ひと昔前はそうじゃなかった。かつての国立競技場も冬になると枯芝で、元旦恒例の天皇杯の決勝戦も、その茶色の草の上で行われるのが当たり前だった。まあショボい話だが、サッカーがマイナー競技だった当時の日本では、誰も文句をいう者はいなかったのだろう。なんたって、草は冬になれば枯れるのが、自然の摂理ってやつだからね。それがサッカー後進国・日本の現実だったわけだ。
しかし、サッカー先進国はそうじゃなかった。当時から東京12チャンネル(現テレビ東京)の、「三菱ダイヤモンド・サッカー」で、ヨーロッパのサッカーをよく観ていた筆者は、向こうのサッカー場の芝生の色に目を奪われていた。なにしろ真冬がサッカーシーズン真っ只中のあちらでは、雪の中でも試合をするのが当たり前。ところがなんと、グラウンドに雪が積もっているのに、サッカーコートの芝生の色だけは、どの会場も青々としているのだ。これはいったい、どういうカラクリなんだ?と、筆者は不思議で仕方がなかった。なんたって、草は冬になれば枯れるのが、自然の摂理のはずだったから…。
ところがこれは、カラクリでも何でもなかった。人工芝でもなければ、もちろん枯芝に緑色のスプレーを吹き付けたわけでもなかったのだ。筆者がこの謎の答えを知ったのは、1993年にJリーグがスタートしてからだったね。どの試合場でもフルシーズンで緑の芝生がキープされており、おお、日本でもやれば出来るじゃん!と、感動したのがキッカケだった。そこで初めて知ったのが、芝生には夏芝と冬芝の二種類があるという事実。つまり、暑い時期には青々としているが、寒くなると枯れてしまうのが夏芝で、反対に暑さには弱いものの、冬の寒い時期に緑色を保つのが冬芝だというのだ。まさに、聞いて驚く意外な事実!
なるほどヨーロッパのサッカー場が、雪の中でも青い芝生を保っていたのは、冬芝のお陰だったというわけだ。逆にサッカー文化が育たなかった日本では、冬でも夏芝のまま放置していて、それが普通だと考えられていたのだ。それを覚醒させたのが、プロリーグであるJリーグの誕生だったのだな。なんたってプロともなれば、試合場のインフラ整備は最重要課題。特にサッカーコートの芝生は、選手たちが活躍する〝檜舞台〟でもある。そこが茶色い枯芝では、選手にも観客にも申し訳が立たないよね。
そこで始まったのが、「ウインターオーバーシード」という育成法だった。これは、寒くなると枯れて休眠してしまう夏芝の上から、冬芝のタネをまいて一年中緑色を保つやり方で、言わば夏芝と冬芝の二毛作みたいなもの。この場合、ベースとなるのは夏芝の方で、一度植えたらそのまま毎年芽を出すが、冬芝の方は単年草の品種を使うため、毎年のタネ蒔きが必要なのだとか。で、春になると伸びた冬芝の葉を短く刈り取って弱らせ、伸びて来た夏芝の葉と徐々に入れ替えるというから、サッカー場の芝生の育成や手入れとは大変なのだ。一年中青い芝生がキープされているのも、スタジアム関係者の努力のたまものだったんだな。
お陰でいまやJリーグの試合は、どこも美しい芝生の上で行われるのが通例となっている。日本サッカーのインフラも、ようやくヨーロッパに追いついたわけだが、この芝生の文化を学校のグラウンドにも広げようと、Jリーグでは応援活動を行なっているらしい。筆者的には、この考えに賛成だ。もし学校のグラウンドが土ではなく、一面の緑の芝生だったらと考えるだけで、何か心がウキウキするようじゃないの。それだけで子供たちは外に飛び出し、きっと走り回るに違いない。なにしろ青々とした芝生は、人の心を元気にする力を持っている。
しかも、芝生の上なら横になっても気持ちがいいし、転んでもすり傷などは出来にくい。そこで弁当を広げ、みんなと一緒に食べるのも楽しいはずだ。まあ、芝生は維持管理が大変だから、という反対意見もあるだろう。だが一方で土のグラウンドは、風の日に土埃を近隣にまき散らす元凶であり、雨の日はドロドロになるという欠点もある。どちらも一長一短だとすれば、やはり美しい緑の芝生の方がマシだと、筆者などは思うんだけどね。だいいち、暖かな春の日に昼寝するにはもってこいだし…。
2022年12月31日
サッカーは何が起きるか分からない

なんだか随分と遠い日のことのように思えるのが、カタールで行われたサッカーのW杯だ。日本時間で12月19日午前零時、つまり18日の深夜に始まったアルゼンチン対フランスの決勝戦は、振り返ってみてもスゴい試合だったなあ。35歳の絶対エース・メッシ率いるアルゼンチンと、23歳の怪物・エンバペ擁するフランスの対決は、最後の最後まで手に汗握る撃ち合いとなった。だが結局は勝負がつかず、PK戦でアルゼンチンの勝利という劇的なフィナーレ。おそらく最後のW杯となるメッシには、ハッピーエンドとなったわけだが、それにしても神様だってこんなシナリオは書けなかったはずだ。
いや、誰もこんなシナリオを書けなかったという点では、わが日本代表の戦いぶりもそれに該当することだろう。何しろ1次リーグのグループEで対戦する相手は、ドイツ、コスタリカ、スペインの3カ国。この組み合わせが決まったとき、ほとんどの日本人は「アイタ~!」と落胆したはずだ。というのも、ドイツ、スペインの2国は世界に轟く強豪国。ともに優勝経験があり、この大会でも優勝候補の一角を占めていた。この2国には良くて1敗1分けと見込んで、コスタリカには必勝し、1勝1敗1分けでなんとか16強入り出来ればというのが、大方の専門家の希望的観測だった。
ところが、開けてビックリ玉手箱。初戦のドイツ戦では前半に1点先取されたものの、後半に攻撃陣全投入という、それまでやったことのない森保監督のバクチあたり、堂安の見事な同点ゴールが決まる。直後には板倉のロングキックを、浅野が一生一度の神トラップから、名キーパー・ノイアーの度肝を抜く逆転ゴール。あとは必死に守りきって、2-1で奇跡的な勝利を奪い取った。日本が真剣勝負でドイツを破るという、世界をアッと驚かせる1勝だったね。
ところが、ここでスンナリ行かないのが森保ジャパン。勝てると見込んだ次のコスタリカ戦では、ターンオーバーが裏目に出て0-1でまさかの敗戦。「やっぱり無能監督」の声が、日本中で溢れたものだ。そして最後にいよいよ、運命のスペイン戦。前半であっさり1点を決められ、もはやこれまでと覚悟を決めた後半、投入された堂安がスーパーゴールを突き刺したときには、筆者も夜明けのテレビの前で、思わず絶叫してしまったね。さらに、三笘の「ウソだろ~!」というセンタリングを、田中碧がヒザで押し込んでついに勝ち越し。日本は2-1の奇跡の逆転勝利で、またまた世界を驚かせた。結果、1位でグループリーグを突破し、「さすがは有能監督」の声が日本中で溢れたものだ。
しかし、絶対勝つはずだったコスタリカに敗れ、ヤバい相手のはずだったドイツ・スペインに日本が勝利するとは、お釈迦様も予想しなかったことだろう。なにより、あの保守的な森保監督が本番の舞台で、攻撃陣全投入という大胆采配を振るうとは、筆者だって考えもしなかった。これは、リハーサルまで声の出なかった歌手が、本番になって人が変わったように、素晴らしい声で歌ったようなもの。人間、いざ本番の舞台に立てば、それまで出来もしなかったことが、出来るものなんだな。いや〜、サッカーは何が起きるか分からない。
残念ながら8強入りを懸けたクロアチア戦では、相手得意の引き分けに持ち込まれ、PK戦のすえ日本は敗退してしまった。だが、大方の予想を裏切ってグループリーグで、ドイツ・スペインを撃破した事実は、日本国内のみならず世界に衝撃をもたらした。なのでYouTubeでは、スタジアムの観客席やスポーツバー、また飲食店や自宅などで撮られた、日本の勝利に狂喜乱舞する人々の動画が、いくらでもアップされていたっけ。なにしろテレビのカメラと違って、撮影したのは一般人。撮った本人がいちばん叫び、かつ飛び跳ねている。ブレまくる画面からは現場の興奮が、臨場感と共にヒシヒシと伝わって来たなあ。
もっとも、日本国内の飲食店や自宅だったら、集まった連中が大喜びするのも良く分かる。だが意外だったのは、スタジアムやその周辺で日本を応援し、祝福してくれる外国人がけっこう多かったことだ。日の丸ハチマキをしたり、サムライブルーのユニフォームを着たりして、一緒に手を叩き喜んでくれる彼らの姿には、筆者もつい胸が熱くなってしまったね。ひとつには地元・カタールが産油国で、石油を買ってくれるお客様の日本には、好感情があったことが考えられる。またイスラム教国の中東人なら、同じアジアの非キリスト教国である日本の方を、応援したくなるのは当然だったろう。それ以外の外国人は、強国ドイツ・スペインに健気に立ち向かう、弱者日本への判官贔屓もあったんじゃなかろうか。
しかしそれらの数多い動画の中で、最も筆者を驚かせたのは、中国のある女子大生がアップしたものだった。そこはどこかの大学の学生寮らしき施設で、大勢の中国人学生が観ていたテレビの大画面に、映っていたのはW杯の日本対ドイツ戦。ワイワイ騒ぎながらみんな試合に熱中していたが、彼らが応援していたのはなんと日本だったのだ。これには筆者もビックリ! なにしろ、反日教育を受けたはずの中国の大学生だ、にわかには信じられなかった。だが最後に日本が勝つと、彼らはもう欣喜雀躍の大騒ぎ。字幕は簡体字だったので、そこが台湾でないのは確か。いったいどうなってんの?と筆者はわが目を疑ったが、いや〜、サッカーは何が起きるか分からない。嬉しかった反面、あれがフェイク動画でなかったことを祈りたいね。
2022年11月30日
食べて驚く意外なモノ

外食などをすると、食べた料理に意外なモノが入っていて、驚いたりすることがある。いい例が、酢豚に入ったパイナップルだ。だいぶ以前、筆者が入ったちょっとお洒落な中華料理店で、これにぶつかった。ランチの酢豚定食を食べていたところ、豚肉やタマネギなどに混じって「ん?」と驚く甘い食材が入っていたのだ。それがパイナップルと気づくまで、そう時間はかからなかったが、これがご飯のおかずなの?と、意表を突かれたのは間違いない。もっとも、油で炒め甘酢で絡めてあったから、味の方はちゃんと美味しかったけどね。
聞くところでは、パイナップルに含まれる酵素の働きで、肉のタンパク質が分解されて柔らかくなるのだという。また糖質、脂質が多い酢豚にパイナップルが加わることで、代謝をサポートしてくれるのだとか。なるほど、単に奇を衒ったわけではなく、ちゃんとした理由があったんだな。ただしこれ、日本人コックのちょっとしたアイデアではなく、中国の清代の頃から料理人はすでに使っていたらしい。当時のかの国でパイナップルは、めったに手に入らぬ高級食材。つまりパイナップル入りの酢豚は、来賓をもてなす高級料理だったというわけだ。
同じ甘い食材でやはり「ん?」と思ったのは、某カレー専門店で食べたベジタブルカレーに、レーズンが入っていたときだったなあ。このときも筆者は、意表を突かれた感じがしたものだ。まあ、レーズンパンなら分かるけど、カレーライスとレーズンを同時に口に入れると、どうしても舌の方が混乱する。なので最初は戸惑った筆者だったが、食べているうちにじきに慣れてしまった。あの甘いツブを噛み砕くたび、塩味に飽きた舌が喜んでいるのが分かった。人間の舌はあんがい適応力があるようで、しまいに筆者はどこか中近東か西域あたりの店で、カレーを味わっている気分になったっけ。
そもそも、甘いフルーツを料理に使うことは罷りならん、という法律は世の中に無いらしい。考えてみれば、リンゴ入りのポテトサラダや柿の白和えなどは、あんがいポピュラーな家庭料理だし、レストランではメロンを生ハムで巻いたものを食べたことがある。もっとも、生ハムメロンは酒の席に出てきた料理だったけどね。あのときは、甘いメロンと塩っぱい生ハムが口の中で混ざり合い、奇妙なハーモニーを生むのが意外だったな。聞くところでは、世間にはイチジクの生ハム巻きというものもあるらしいが、筆者はまだ出会ったことがない。何でも生ハムで巻けば良い、というものでもないと思うんだが…。
だが、野菜は塩分で味付けして料理に使い、甘いフルーツは食後のデザートという考え方は、人間が勝手にこしらえた固定概念かも知れないな。だいいち、野菜だって砂糖で味付けすればデザートに早変わりする。日本では小豆を砂糖で煮込んで、餅や饅頭のアンコとして使うのが当たり前だが、豆を煮込み料理の具材と考えている外国人は、これを見てビックリするようだ。「オー、アンビリバボー!」。だが、食べてみて二度ビックリで、最近は大福餅の美味さにファンになる外国人も多いらしい。何ごとも食べてみないと分からないもの。筆者も大福餅や羊羹は好物なのだ。
そんな外国人がさらにビックリするのが、コンビニでよく見かけるフルーツサンド。柔らかい食パンに、生クリームとイチゴやパイナップル、メロンなどのフルーツを挟んだ、日本生まれのサンドイッチだ。筆者はまだこれも食べたことがないが、主食なのかお菓子なのかよく分からないのに、全国で静かなブームになっている不思議な商品らしい。そもそもサンドイッチはイギリス発祥の、パンにハムや野菜を挟んで食べる簡易食。トランプをしながら食事が出来るようにと、サンドイッチ伯爵が考案したものと言われている。この人物、食事の時間も惜しむほどの、よほどの賭博好きだったらしい。
なので、サンドイッチを主食の一つと考えている外国人は、日本で出会ったフルーツサンドに目をシロクロのようだ。何といってもパンの間に、甘い生クリームとフルーツが収まっている。やはり「オー、アンビリバボー!」だろうね。ところが、これを食べた彼らはあまりの美味さに「オー、マイ、ガー!」。ユーチューブには、フルーツサンドを初めて食べて感動する、彼らの動画がいくらでもアップされている。見てビックリ、食べて納得、というやつだ。考えてみれば、パンに生クリームにフルーツだから、ケーキの一種と言えば言えないこともないが、見た目がサンドイッチというところが、彼らの常識外だったんだろうな。
そこで思い出すのが、アメリカ生まれの巻き寿司・カリフォルニアロールだ。なんと寿司の具材にアボカドが使われており、今度は日本人がビックリさせられた。「冗談はやめろよ!」。なにしろ日本の伝統料理と、熱帯生まれの果実の取り合わせだから、初めてそれを聞いた日本人はやはり頭を抱えたね。しかしこのカリフォルニアロールが、アメリカ人を寿司に目覚めさせたとすれば、筆者もいまさら否定する気はない。というか、アボカドはワサビ醤油と意外なほど合うので、食べてみればけっこうイケるんじゃなかろうか。まあ、その気はないけど。しかし地球が狭くなった現代では、これからも意外な食材の組み合わせから、常識破りの料理がどんどん生まれることだろう。たとえば、ドリアンと鮒寿司とくさやの和え物とかね…。
2022年10月31日
さらば、アントニオ猪木

アントニオ猪木が亡くなってからしばらく経つが、いまだに喪失感にとらわれているファンも多いのではなかろうか。筆者もその一人で、なんだか昭和のプロレスそのものが燃え尽き、消えてしまったような寂しさを感じるな。アントニオ猪木は間違いなくその中心にいて、輝き続けたプロレス界の巨星だった。晩年は難病との闘いでずいぶん痩せてしまったが、その姿をさらけ出して堂々と動画配信するなど、最後までカッコ良さを貫いた強い男でもあった。もっとも筆者などは、見るのがちと辛い動画だったけどね…。
思い出すのは、1998年4月4日の猪木の引退試合だ。あの日は筆者も、プロレスファンの友人たちと東京ドームに駆けつけ、客席から声援を送ったものだった。その引退試合の猪木の相手は、トーナメントで小川直也を破って勝ち進んだドン・フライ。え、直弟子の小川じゃないの?と誰もが思ったが、そこはアメリカUFCチャンピオンのドン・フライの方が、真剣勝負らしい緊迫感が生まれるという筋書きだったのだろう。事実、会場はおおいに盛り上がった。ただし筋骨隆々のフライに比べれば、すでに55歳で筋肉も落ちた猪木の肉体は、どこかほっそりと頼りなくも見えたっけ。
だが観客をハラハラさせ、最後に勝つというのが猪木の真骨頂だ。この試合では、猪突猛進する相手を得意のプロレス技で痛めつけ、フィニッシュは電光石火のグランドコブラでギブアップ勝ちという、見事な試合を見せてくれた。まあ引き立て役のフライも大変だったろうが、やられっぷりは悪くなかった。というか猪木のリードで無事に大役を果たし、ホッとしたというのが真相だろう。なにしろ世界的レスラー・猪木の最後の相手として、プロレス史に名前が刻まれるのだから、フライとしても悪い話ではなかったはずだ。
振り返ってみれば、全盛期の猪木ほど名勝負を生み出したレスラーもいないだろう。日本プロレス時代の対ドリー・ファンク・ジュニア戦やジャック・ブリスコ戦もよかったが、なんと言っても印象的なのは日プロを飛び出し、新日本プロレスを設立してからの熱戦の数々だ。なにしろ金もなければテレビ中継もなく、招聘する外人ルートもロクにない中の船出。対戦相手となる外人は、無名の選手を発掘し自分で育てなければならなかった。そんな中で生まれた最初のスターが、タイガー・ジェット・シンだったな。
有名な〝新宿伊勢丹事件〟で世間の注目を集めたシンは、たちまち新日本プロレスの外人エースとして売り出してゆく。なんたって〝インドの狂虎〟だ。狂ったようにサーベルを振り回して試合場に乱入し、猪木を血だるまにして暴れまわる姿は、日本中のプロレスファンの度肝を抜いた。あのコブラ・クローは恐ろしかったね。だがもともとシンは、フレッド・アトキンス(G・馬場のコーチも務めた人物)に手ほどきを受けた実力派レスラー。地元カナダでは、ベビーフェイスだったというから驚きだ。
そのシンを大悪党レスラーに育て上げたのは、むろん他ならぬアントニオ猪木だった。素顔はジェントルマンのシンに、〝インドの狂虎〟のキャラクターを与え、試合では血だるまになって技を受ける。むろん最後は猪木が勝つのだが、社長レスラーとはかくも大変な仕事なのだな。シンも期待に応え、つねに伯仲した好勝負を見せてくれた。おかげで新日は、営業的にウハウハだったはず。実はシンにサーベルを持たせるアイデアは、猪木の発案だったと言われている。自分が発案した凶器で血だるまにされる姿は、かつて〝吸血鬼〟フレッド・ブラッシーに額を噛まれては大流血していた、師匠の力道山の姿を彷彿させる。ブラッシーはヤスリで歯を磨くパフォーマンスが得意だったが、その発案者は実は力道山だったというわけ。プロレスはこういうところが面白い。
シンの他にも猪木は、アメリカで一流未満だったスタン・ハンセンやハルク・ホーガンといった大型レスラーを、新日のリングで外人のエースに育て上げている。そこにはビッグバン・ベイダーも入るだろう。ハンセンのウエスタン・ラリアットに吹っ飛ばされ、ホーガンのアックスボンバーにKOされ、ベイダーの巨体に押し潰され、猪木の体はよく壊れなかったものだ。だが、そこが猪木の猪木たる所以なのだろう。多くの日本人レスラーを弟子として育成しながら、また対戦相手の外人レスラーも数多く育てたところに、この男の真価があると言えそうだ。彼の死を悼み懐かしむ声は、内外のマット界から聞こえてくる。
とにかく猪木は、レスラーとして優れた才能に恵まれていたと同時に、対戦相手の能力を引き出すことにかけても、類い稀な才能を持っていた。新日旗揚げ以降の名勝負を数えても、とても筆者の10本の指では数えきれない。対ハンセンやホーガン戦の他にも、ビル・ロビンソン戦、ウィレム・ルスカ戦、アンドレ・ザ・ジャイアント戦、ブルーザー・ブロディ戦など、枚挙にいとまがない。またストロング小林戦や大木金太郎戦、ラッシャー木村戦など、日本人対決にもシビれさせて貰った。そういえば、ヨーロッパ遠征でのローラン・ボック戦というのもあったなあ…。
忘れられないのがプロレスの埒外の、モハメド・アリ戦やアクラム・ペールワン戦、ウィリー・ウィリアムス戦といった真剣勝負だ。これらはプロレスファンをヒリヒリさせ、すべての格闘技ファンに夢を見させてくれたものだ。いまではプロレスは、明るいエンタメとして定着した感があるが、もうあの頃の血が沸騰するような興奮は、二度と戻って来ないんだろうなあ。筆者的にはそこが寂しいのだ。さらば、アントニオ猪木! 後にも先にも、もうこんなレスラーは出て来ないよね。
2022年09月30日
ヨーロッパ映画の苦い味

筆者は最近、映画館に行く機会がめっきり減ってしまった。なにしろ佐賀は映画館の数が極端に少ないので、観に行くとすれば車かバスか電車に乗って、遠いシネコンまで出かけるしかない。これがけっこう億劫なのだ。かつて東京に住んでいた頃は、巨大な街のあちこちに映画館があり、ブラリと気軽に行くことが出来た。買い物のついでにちょっと立ち寄ったり、打合せと次の打合せのあいだの時間潰しに入ったり、ときには終電を逃してオールナイトの上映館で夜を過ごしたり…。筆者にとって本来、映画館とはそんな存在だった。なので、♫は〜るばる行くぜ映画館へ〜、という面倒なプロセスはどうも気が滅入るのだ。
そんな出不精の映画好きの強い味方が、かつてはビデオテープだった。それがDVDになりブルーレイに進化し、近ごろそれらに取って代わったのがインターネットによる配信だ。いや~、時代は変わるもんだ。なんたって電話線のおかげで、自宅で映画が観られるようになったのだから、かのグラハム・ベルも腰を抜かすはず。これなら、佐賀のような田舎に住んでいても何の不便もない。その恩恵で筆者も自宅のイスにひっくり返って、じっくり映画を楽しめるようになったわけだが、ありがたい世の中の到来じゃないか。
ネット配信の良いところは、メニューの数が多い点だろう。とにかく、邦画も洋画も新作から旧作まで、いろんな作品を自分で選んで観ることが出来る。佐賀の映画館ではまず上映されないような、レアな映画だって探せば出て来る。そこがまた面白い。筆者の楽しみは、あまり話題にならなかったような作品の中から、シブい名作を見つけ出すことで、これだ!というものに巡り会ったときは、道で大金を拾ったような気分になる。ただしハズレに当たったときは、時間を返せこのヤロー!と叫びたくもなるが…。
最近、筆者がハマっているのは、ヨーロッパ映画だ。これが実に奥が深い。まあ、ひとくちにヨーロッパ映画と言っても、フランス映画もあればイギリス映画もあり、ドイツ映画だってイタリア映画だって健在だ。また北欧の映画も、捨てがたい独特の味を持っている。総じて言えることは、世界を席巻するアメリカ映画に比べれば、それぞれ国ごとに違った個性があり風味があるということだ。しかもこの個性や風味には、長い歴史を経て来た絶妙なスパイスが利いている。そこが魅力なのだ。アメリカ映画が大通りに立つ電飾ギラギラの巨大デパートだとすれば、ヨーロッパ映画は迷路の奥に点在する謎めいた専門店といったところだろうか。
たとえば、アメリカ映画に慣れた目でヨーロッパ映画をみると、感じるのは雰囲気の暗さだ。まず、空の色が暗い。これは緯度の関係もあるのだろうが、ヨーロッパの空はどことなく暗く重い。とくに北欧の映画は昼間でも薄暗く、それが画面全体に重苦しい陰影を与えている。筆者が4本観たデンマーク映画『特捜部Q』シリーズは、過去の迷宮入り事件を再捜査する特捜部を描いたものだったが、明るく晴れた空はどこにも出て来なかったな。おまけに、主人公の刑事も暗い過去を持つ無口な男。いや暗い過去を持つのは犯罪者たちも同じで、そこからは階級差別や移民問題、貧富の差など、ヨーロッパが抱える病巣が透けて見えるのだ。つまり何もかもがひどく暗い。だけど、この暗さに慣れてしまうと、病み付きになるんだよね。
暗い空に荒れた海、そこに荒涼とした原野や古い城が加われば、まさにこれヨーロッパ映画だ。何気なく見始めたフランス映画『燃ゆる女の肖像』は、そんなシチュエーションで展開する作品だが、登場人物がなぜか女性ばかり。ひょっとしてこれはと思っていたら、やはりそっちの方に話が進み、女どうしの激しい恋が燃え上がるという筋書きだ。ただし、アメリカ映画のような野暮な性描写などはなく、二人の女性の感情を押し殺した短いセリフのやりとりと、絵画のような映像美が印象的な佳作だった。それが映画に品を与えていたが、やっぱり演技は抑制的なのが良い。しかしこういう耽美的なものは、やはりフランス映画に限るなあ。
ドイツ映画『コリーニ事件』は、富豪を殺害したイタリア人・コリーニの弁護を引き受けた、トルコ移民の子である若い弁護士が主人公だ。ここでも移民への差別や、旧ナチスの戦争犯罪といった、ドイツが引きずる社会問題が影を落としている。単純に見えた殺人事件の裏には、この国ならではの深い傷が隠れているというわけ。また、ポルトガル映画『カルガ 積荷の女』は、売春組織による女性の人身売買を描いたものだが、ここにも貧困や差別、暴力といった、ヨーロッパの抱える病巣が描き出されていた。とにかくこの殺伐とした絶望感は、アメリカや日本の映画では絶対に描けないものだろうな。
ヨーロッパ映画を観て感じるのは、どれもセリフが抑制的で音量も控えめということ。だいたいが、静かな映画が多いのだ。アメリカ映画みたいに、やたらと大声を出したり怒ったりという場面は少ないし、日本映画のような説明的長ゼリフもオーバーな演技もない。淡々とリアルに物語は進行し、やがてその先に皮肉で悲劇的なラストが待っている。なので、ドラマチックな展開やド派手なアクションが好きな人には、少し退屈に映るかもしれないな。だが、その退屈さをガマンして乗り越えると、最後にアメリカ映画では感じられない、複雑で味わいの深い感動を得ることが出来るのだ。
といっても必ずしも、ハッピーエンドが待っているわけではない。ヨーロッパ映画のいちばんの特徴は、ラストが甘くないところだろう。いや、甘くないというよりけっこう苦い。だがその深い苦味の中に、煮ても焼いても食えないヨーロッパの本質があり、捨てがたい余韻があるのだ。ビールだってウイスキーだって、苦味があるからこそ美味いはず。ハッピーエンドが好きな人は、コーラを飲みながらアメリカ映画を観ればいい。これはどっちが良いというわけではなく、ラストの苦い味をしばらく引きずりたい人には、ヨーロッパ映画がオススメということだ。実は甘いお菓子も大好きな筆者なのだが、この秋は苦味のきいたヨーロッパ映画をしばらく楽しみたい。
2022年08月31日
日本の無人販売所
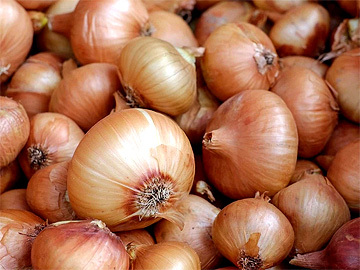
筆者の散歩コースに一軒の農家があり、そこの小屋の軒下は野菜の無人販売所になっている。台の上には、袋詰めになった野菜と赤いポストの貯金箱が、無造作に並べてあるだけ。野菜はどれもひと袋100円なので、利用者は貯金箱の中にチャリンとコインを入れ、商品を自由に持ち帰れば良い。この気安さと野菜の量の多さが気に入り、筆者も散歩の帰りにときどき利用させてもらっている。なんたって採れたて野菜が、これでもかとビニール袋に詰め込んであるのが良い。
で先日は、筆者が玉ねぎの袋を購入したところ、たまたまそれを見ていた店のオヤジに呼び止められてしまった。と言っても「このコソ泥が、ちょっと待てコラ!」といった乱暴なものではない。なにしろ筆者は、貯金箱にちゃんとコインを入れている。オヤジさん曰く「ミニトマトやピーマンなど、採れた野菜が余って困るけん、タダで持って行ってくれんね」ということだった。むろん、遠慮する理由はない。筆者は彼が袋いっぱい詰めてくれた、ミニトマトやピーマン、シシトウなどを、ありがたく頂戴して帰ったのだった。
農業県・佐賀に住む最大のメリットは、こうした野菜や果物などが、比較的安く(ときにはタダで)手に入ることだろうか。まあ、東京などの大都会ではこうはいかないもんな。だいいち農地が少ないし、仮にそんな奇跡のような無人販売所があったとしても、黙って商品を持ち帰る不届き者があとを絶たないはず。いやその前に、料金箱ごと盗まれる可能性がそうとうに高い。まして、採れた野菜をタダでくれるような奇特な人など、皆無なんじゃなかろうか。
こうした心温まる無人販売所が成り立つのは、やはり日本でも都会ではなく地方なのだろう。それも、悪質な外国人などのいない地域に限られる。つまりお互いが性善説を信じ、信頼関係で結ばれた善良な人々の暮らす町や村だ。そういう意味ではアジアの島国・日本には、まだまだ古き良き伝統を残す地域が数多く存在するはず。世界から訪れた人々が無人販売所を見てビックリするのは、自分たちがとうに失ったモラルが、日本の田舎にはごく普通に残っているからだろうな。
そもそも日本には、「お天道様が見ている」という言葉がある。他の誰かが見ていなくても、空にあるお日様はちゃんと見てるぞという戒めだ。なのでたとえ無人の販売所だろうと、誰もいない自動販売機だろうと、悪いことは出来ないよう日本人は子供の頃から躾けられている。あのフーテンの寅さんだって、「お天道様は見ているぜ」と言ってたものな。つまり、人間の目を超越した〝太陽の目〟を意識することで、日本人は自分を律しているわけだ。なにしろ国号を「日本」と言い、国旗に日の丸を掲げるほど、われわれはお日様を愛しているからね。
もっとも、この人間の目を超越した目とは、場合によってはお日様に限らないのかもしれない。そもそも太陽は夜には隠れてしまう。言わば、夜間には稼働しないソーラーパネルみたいなものだ。そこで、あるときはお月様の目だったり、神社の千年杉の目だったり、地域にある霊山の目だったり、道端のお地蔵様の目だったりと、われわれは常に人間ではない何者かの目によって、見られることを意識している。つまり、身の回りの至るところに神仏がいて、悪いことをしないよう昼も夜も監視しているわけだ。日本人は無宗教と言われるのに犯罪率が低いのは、こうした柔軟で実利的な防犯システムを、誰もが心の中に持っているからだろうか。
だが世の中、そんなことに無頓着な悪い奴はいるもの。たとえ100円の野菜でも、料金を払わず無断で持ち帰れば窃盗の罪になる。窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められており、起訴された場合はこの範囲で刑罰が下されるという。なので軽い気持ちでイモの袋を持ち帰ったりすると、後でとんでもないことになりかねない。無人販売所は購入者の良心を信頼して店を開いているので、そんな信頼を裏切っちゃあマズイのだ。やっぱりコソコソと盗んだ野菜を食べるより、堂々と購入した野菜を食べる方が、ずっと美味で消化も良いんじゃなかろうか。
そういえば、小城ではそろそろミカンの実る季節だ。筆者の秋の恒例行事である八天山神社への山登りは、たいてい下りに清水の宝地院の門前を経由することになっている。するとそこにはいつも、ミカンなどの無人販売所が設置してあり、疲れた体と心をホッコリさせてくれるのだ。良いんだよな、この光景が。誰もいない山中を抜けて、いかにも里に降りて来たという実感がする。なので今年も筆者は、ミカンをひと袋買うことにしようかな…。
2022年07月31日
美味いものが食べたい

日本を訪れる外国人観光客にも、お目当てのものが色々あるようだ。その中でよく聞く声は、日本の食べ物を食べることだとか。彼らにとって日本での食事は、大きな楽しみの一つらしい。和食はユネスコの無形文化遺産に登録されたほどだし、いまや世界中が日本の伝統的食文化に高い関心を持っている。食材は新鮮だしヘルシーだし、おまけに見た目は美しいし──とね。だがそんな理屈は横に置いても、和食に限らず日本には多種多様な食文化が花開いている。
なにしろお金さえあれば、寿司に天ぷら、すき焼きにしゃぶしゃぶ、うなぎの蒲焼や和牛ステーキなど、いくらでも高級料理が楽しめる。お金のない人も街を歩けば、牛丼やカレーのチェーン店から、うどんや蕎麦といった麺類の店、また町中華のラーメンに餃子、居酒屋のおでんに焼き鳥など、安いメニューがより取り見取りだ。つまり、どこに行っても美味いものが味わえるというわけ。しかも日本は北から南まで細長く、郷土料理も種々様々ときている。
日本の食べ物に詳しい外国人ユーチューバーが言うには、日本は都会から田舎まで美味いものの宝庫だそうだ。それも高級料理店はもちろんだが、そうでない庶民的な店に入っても、ちゃんと美味いということが感動的らしい。われわれ日本人の感覚からすれば、高い店だろうが安い店だろうが、金をとる以上は美味いものを出すのが当たり前。だが、どうも外国はそうではないようだ。高い店が美味いものを出すのは当然として、安い店はまあそれなりの味というのが、どうやらむこうの常識らしい。なので、日本で安くて美味い店に出くわすと、彼らはいたく感動するんだとか。
日本の料理が外国人を感動させるのは、やはり料理人の腕が良いということだろう。そこからはものづくりに拘る、日本人特有の職人魂が見えて来る。安かろうが高かろうが、とにかく味にこだわる頑固な職人が、日本にはたくさんいるからね。一流店のシェフや板前さんから、町のラーメン屋のオヤジまで、完璧を目指す精神はみな同じ。仕事場は神聖なる道場であり、道を極めるためには人生を賭けるという、まるで刀鍛冶みたいなプロフェッショナリズムが、そこにはありそうだ。好きなんだよね、日本人はこういうのが。
テレ東で放送しているドラマ『孤独のグルメ』には、そんな無名の職人たちが何人も登場する。主人公の井之頭五郎が商談に出かけた先で、たまたま見かけた店に入るというストーリーだから、出て来る店はたいてい大衆食堂とか町の中華屋、洋食屋などだ。番組ではそうした実在する店で、コツコツ地道に働く隠れた名人にスポットを当て、あたたかな視点で紹介している。誰もが誠実で真摯に味に向き合っているところに、筆者などはいつも感心するのだ。ただし、観ているうちに腹が減るのがちとツライけど…。
だが何といっても、日本の料理がどれも美味いのは、料理人が出汁(だし)に拘るからだろう。出汁──つまり、うま味だ。世界中で日本の料理人ほど、出汁に拘る人々はいないんじゃなかろうか。なにしろ、この「うま味」を世界で初めて発見したのは、日本人の化学者・池田菊苗博士なのだ。池田博士は1908年に昆布の煮汁から、うま味の素であるL-グルタミン酸ナトリウムを抽出したわけだが、これを製品化したものが筆者も愛用する「味の素」。甘味、酸味、塩味、苦味に次ぐ第五の味「うま味」は、そのまま「UMAMI」として世界でも使われるようになった。
もっとも「うま味」の発見以前から、日本の料理人はいろんな食材から出汁が取れることを知っていた。前述の昆布からはグルタミン酸を、鰹節からはイノシン酸を、またシイタケからはグアニル酸をという具合に、自分の経験や先人の教えなどから、上手に出汁を取っては料理に活かしてきたのだ。つまり伝統的に、日本の料理はまず出汁ありきということ。これはプロの料理人に限らず、ふつうの家庭でも同じことだろう。毎朝食べる味噌汁も、冬場に囲む寄せ鍋も、そもそも出汁がなかったら始まらないのだ。
かつてチェルノブイリ原発の爆発事故の後、放射性物質を体外に排出させる作用があるとして、味噌が日本からヨーロッパに輸出されたことがあった。筆者には当時の、泣きそうな顔をして味噌汁を飲む、むこうの子供達の映像が印象に残っている。あのとき可哀想だと思ったが、いまから考えればきっとあれには、出汁が入ってなかったんだろうね。そりゃマズいはずだ。外国人に味噌を送るんなら、鰹節も一緒に送ってあげないとな。
まあ、こんな〝出汁の王国〟日本だから、和食はもちろんのこと洋食だろうが中華だろうが、厨房の板前さんもコックさんも、腕によりを掛けて出汁をとっているはず。動物性に植物性と、様々な食材にはそれぞれのうま味が含まれている。どんな食材からどんなうま味を引き出し、どう調合するかが料理人の腕の見せどころだ。職人魂で日々研鑽を重ねている彼らのおかげで、日本中どこに行ってもわれわれは美味いものが食べられるというわけ。外国人には、そこが感動的なんだろうね。
2022年06月30日
冗談が通じない

あまりテレビを観ないので、エラそうなことは言えないが、最近はどうもこれといったお笑いタレントが少ないような気がする。筆者が言うのは、話の面白さについ引き込まれ、さんざん笑わされた後、さすがだなあと感心させるような、そんなタレントのことだ。つまりセンスが良くて頭の回転が速く、面白いネタをまるで手品のように次々と取り出してみせては、自分はすまし顔でそっぽを向いている…。こう言うと、まるでかつての立川談志師匠みたいだが、筆者の好みはそんな江戸風のお笑いだ。
逆にあまり好きじゃないタイプというと、関西系のコテコテしたお笑いだろうか。声が大きく身振り手振りが大仰で、ネタはさほどでもないが、とりあえず関西弁のノリの良さに乗って、パターン通りの味付けで笑わそうというやり方だ。これ、最初は面白いが筆者などはすぐに飽きてしまうんだよね。特に嫌いなのが、顔で笑わせようとするタイプで、これはズルイというものだ。そこへ行くと関西の芸人でも、桂米朝師匠などは品があって話芸も芸術品だったし、松本人志のとぼけたアドリブ芸も味があって捨てがたい。
もっとも、他人を笑わせてそれを商売にするというのは、凡人にはとうてい不可能なこと。よほどの才能と努力がなければ、その世界でメシを食うことなど出来はしないはずだ。われわれ一般人だって、日常会話で他人を笑わせるには、それ相応のネタやアドリブや話のうまさが必要になる。それが出来るようになれば〝面白い人〟と呼ばれるが、出来なければ〝普通の人〟として聞き役に回るしかない。まあ〝普通の人〟も、世の中的には必要なのだが。
ところで佐賀県人は、どうも「クソ真面目」というのが通り相場らしい。これは、佐賀にずっと住んでいれば分からないが、他県に出たときハタと気がついたりする。いわば県民性というやつだ。最近は、はなわやエガちゃんやどぶろっくのような、佐賀県出身のお笑いタレントが東京で活躍しているが、彼らの笑いの根底にも「クソ真面目な佐賀県人」を逆手に取った、田舎者の自虐性が秘められているような気がする。まあ、それだけ彼らもしたたかということだろう。
筆者も初めて東京に出て行った学生のとき、友人から「お前はクソ真面目だ」とよく言われたものだ。つまり向こうが軽い冗談を言っても、ついクソ真面目な答えをしてしまい、座を白けさせてしまったりしたからね。いまでは筆者も、冗談には冗談で切り返すことを心得ているが、あの頃はそれがカルチャーショックだったなあ。これもやっぱり、佐賀の「葉隠」文化の影響なのだろうか。佐賀のスタンダードが、東京のスタンダードではないと知ったときは、筆者もちょっと考えてしまったね…。
しかし「クソ真面目」なままでは、人間関係もうまくいかない。そこで筆者も、ない知恵を絞って考えた。まず山上たつひこのギャグ漫画を熟読し、山上流ナンセンスギャグの習得に努めたのだ。これはけっこう勉強になったっけ。それから当時はラジオの深夜放送の全盛期で、「オールナイトニッポン」でDJをやっていたのが、タモリとビートたけしの両巨頭。この番組には他にも有名タレントが多数出演していたが、何といってもタモリ・たけしという、二人の天才の話は抜群に面白かったね。筆者は彼らのギャグや喋り方などからも、ずいぶんと影響を受けたものだ。
こうして刻苦勉励・艱難辛苦のすえ、田舎者の筆者もようやく東京というカオスの中で、人並みに軽い冗談のやり取りが出来るようになった。ただしこの場合、冗談はあくまで軽くアドリブの利いたものが重要で、家を出るときから考えて来たようなものではダメ。当意即妙のこうしたジャブのやり取りをしているうち、「お主、出来るな」と相手も認めてくれるというわけだ。ことほど左様に、冗談の分かる男になるのは難しい。ふう、たいへんだ…。だが〝面白い人〟と呼ばれるようになれば、人間関係も大いに広がり、仕事や友人との付き合いも楽しくなる。
ところが、世の中はうまくいかないもの。長い東京生活を終えて佐賀に帰った筆者が、現在感じていることは、まわりに冗談が通じないということだ。すました顔で冗談を言い、相手を笑わせるのが得意ワザの筆者だが、佐賀ではどうもこれがうまく伝わらない。やっぱり佐賀の県民性という奴だろうか。せっかく冗談を言っても真面目な顔で答えられると、肩透かしをくらった相撲取りみたいで、筆者はつい土俵の砂をぶちまけたくなってしまうのだ。なんで分かってくれないの!?
むろん佐賀県人の「クソ真面目」は、悪いことではない。「佐賀人の歩いた後には草も生えん」と巷で言われるのは、勤勉・倹約・実直を美徳とする県民性から来ているのだろう。なので仕事はキッチリやるし、狡いことは出来ないタイプ。ゆえに融通が利かないところもあるが、他県人からは信用される。そこにもう少しゆとりと言うか、柔らかなユーモアのセンスがあればと筆者は思うのだが…。
2022年05月31日
安宿一人旅のススメ

猫も杓子もユーチューバーという時代だが、とにかくネット動画の世界は様々なコンテンツであふれている。いまは若者からお年寄りまで、また有名人も無名の素人も、自分で企画を立て撮影・編集し、自由に動画をアップ出来る世の中なのだ。しかもみんなけっこう良いカメラを使っている。テレビの地上波番組などより、ずっと高画質で臨場感のあるものも多い。そんな玉石混交のコンテンツの中から、掘り出し物の番組を探すのはあんがい楽しいものだ。
素人がつくる番組で多いのは、食べ歩きや旅行のリポートなどだが、カメラ一つあればわりと簡単に一本撮れてしまうので、彼らには取っ付きやすいテーマなのだろう。ただし、食べ歩きも高い店ばかり選んでいると経費が嵩むし、遠方への旅行や高級旅館でのお泊りは、交通費や宿泊代がバカにならない。それに誰もが知っている店や観光地の紹介では、視聴者の耳目を集めるのは難しいはず。素人の番組には素人ならではの、ユニークさが求められるのだ。
そんな素人の番組の中で面白いのは、筆者的にはやはり旅行ものだろうか。それもテレビの紀行番組を真似たような、とりすました観光地のリポートではなく、誰も行かないような地方の町を探索し、一人で安宿を求めて歩くようなものが良い。なぜなら、テレビではそんな番組は絶対に作れないからだ。テレビでは気楽な一人旅のように見せてはいても、実際にはシナリオがあり、カメラの後ろには大勢のスタッフがいる。またタレントもそんな安宿に、一人では泊まりたがらないだろう。そうではなく、正真正銘の安宿一人旅を撮れるのは、やっぱりユーチューバーにしか出来ない芸当なのだ。
筆者がそんな一人旅の番組を愛するのは、自分もずいぶんと一人旅をして来たからかもしれないな。思えばいろんな所へ行ったもんだ。一人旅の良いところは、とにかく思いきり自由を満喫できる点。引率された団体旅行の窮屈さもなければ、同行者への気兼ねでストレスが溜まることもない。何から何まで自分でスケジュールを決め、自分の判断で行動するのが一人旅のルール。つまり天下の素浪人になったつもりで、誰にも束縛されず、旅そのものを楽しめるのが最大の魅力と言えようか。
もっとも一人旅と言っても、愛好者にはそれぞれの楽しみ方や目的があるだろう。名湯秘湯を求めてという人もいれば、美味いものが食いたいグルメ派や、ローカル鉄道が好きという乗り鉄もいるはず。筆者の場合は、日本の古い町並みを歩くのが好きだったね。いわば、町並みオタク。なので、旧城下町や宿場町に寺内町など、時代の本流から取り残されたような各地の古い町を探しては、よくブラリとそこを訪ねたものだ。そして、観光客などいない静かな通りを一人で歩きながら、千本格子や漆喰壁の残る美しい家並みを、じっくり堪能し写真に収めるのが楽しみだった。そこで、筆者はまるで時間旅行をしているような、不思議な至福のひとときを味わうことが出来たってわけ。
で、当然ながら泊まるのは、たいていそんな寂れた町の旅館ということになる。これがまた風情があって良いんだよな。筆者がよく利用したのが、ビジネス旅館や商人宿といったその道の玄人向け旅館。これは一般観光客はあまり来ないが、行商人やビジネス関係の人がよく利用する、低価格の小ぢんまりした旅館だ。言ってみれば、普通の観光客向け旅館と民宿の中間的な存在だろうか。なので多くは家族経営だが、そのぶんアットホームな雰囲気が味わえる。何といっても一泊二食付きで○千円という、安心価格なのが最大の魅力なのだ。
むろん、部屋は豪華でも広いわけでもないし、立派な大浴場があるわけでもない。夕食の献立だって、板前さんが腕を振るった見栄えの良い料理が出て来るわけではない。普通はその宿のオヤジやおかみさんが作ってくれる家庭料理だが、なにしろ客の数が少ないぶん心がこもっている。安い宿代のわりには刺身とか天ぷらとか、これで良いの?とこちらが心配したくなるほど、サービスが良いのが常だった。人間、初めから高望みさえしなければ、それなりに満足を得られるものなんだな。
そんな安宿で一人で寝ていると、深夜になんだかしみじみした気分になったりするものだ。ああ自分はいまどこに居るんだろうと不安になったり、あるいはずいぶん遠くまで来たものだと感慨に耽ったり…。それもまた旅情というものかも知れないが、これは一人旅でしか味わえない孤独感なのだろう。でも、これも一人だから楽しめること。もし家族旅行でこんな部屋に泊まったら、たぶん誰もがとんでもなく暗い気分になるはずで、子供なんか泣き出すかも知れないな。ああ、怖いねえ。
そうそうアットホームな雰囲気といえば、あれは岐阜県のある町の小さな旅館に泊まったときのこと。風呂に入った筆者が驚いたのは、浴室のあまりの狭さだった。まあ一人だから良いだろう、と置いてあったシャンプーや石鹸を使いながら、体を洗っていたらそこにもう一人の客が入って来た。「ずいぶん狭い風呂ですね」などと談笑した後、先に出た筆者がふと廊下の向こうに目をやると、そこには客用の浴室の扉が見えたっけ。うっかり者の筆者は、旅館の家族用の風呂に入ってしまったのだった。あのとき話しかけた相手は、そこの家のお爺さんだったのだな。まあ、こんな失敗も旅の良い思い出というやつだ。
古い町並みが残るところでも、中堅クラスの地方都市になると、たいていは駅前にビジネスホテルがある。筆者はそんなホテルもよく利用したものだ。ビジネスホテルの長所は価格が安いことと、完全にプライバシーが守られることだろう。チェックインから翌朝のチェックアウトまで、客は誰にも気を遣うことなく一人で自由を味わうことが出来る。それはそれで楽チンなのだが、旅の記憶にあまり残らないのは、そこに人間との触れ合いがないからだろうね。やはり当たり外れがあるとは言え、その土地の宿で受けた土地の人による様々な心尽くしが、振り返ると旅の記憶の大きなポイントになっている。そういえば筆者は最近、古い町並みを歩いてないが、なんだかまた何処かへ行きたくなって来たなあ…。
2022年04月30日
激辛料理と日本人

よく日本人は辛いものが苦手だと言われる。たしかに同じアジアでも周辺の国々と比べると、日本には伝統的に辛い料理が少ない気がする。すぐ隣の朝鮮半島には赤唐辛子タップリの料理が多いし、中国料理にも激辛ものがたくさんある。これが東南アジアやインドあたりに行けば、料理とは辛いのが当たり前とか言われそうだ。あっちの国の人々は、唐辛子をボリボリかじったりするからなあ。
考えてみれば日本を代表する料理って、すき焼きにしろ天ぷらにしろしゃぶしゃぶにしろ、辛さとはほとんど無縁なのだ。いやいや、寿司や刺身にはワサビが付きものという人もいるが、あれは辛いというより鼻にツンと来るタイプだから。唐辛子や胡椒などをふんだんに使った、口や食道や胃の中が火事になるような、近隣国の料理に比べれば、ワサビなどはひと時の清涼剤みたいなもの。本当の激辛料理はトイレにまで追いかけて来るから、胃腸の弱い日本人には厄介なのだ。
そういえば筆者が若いころ、仕事の打ち合わせに出かけた会社でのこと。打ち合わせが終わり昼になったので、先方の友人二人と食事に行くことになった。で、連れて行かれたのが一軒のカレー専門店。くだんの二人が頼んだのは、なんと辛さが最高ランクのカレーだった。負けるもんかと筆者も同じものを頼んだが、さすがにこれはキツかったね。だが、ニヤニヤしている二人に弱音を吐くのもシャクなので、ガマンして平気な顔で一皿食べ終えたのだった。ただし、しばらく経ってトイレに行きオシッコをしたとき、尿道にビリッと電流が走ったのには驚いた。いや~、あれは体が震えるようなショックだったなあ。
そうそう、筆者がかつて台湾に行ったときも、けっこう辛い料理を連日食べたっけ。そして、旅行の日程が終わり最後の日に案内されたのが、わりと庶民的な台北の台湾料理店。ジューシーな小籠包など、そこで食べたものはどれも美味かったが、調子に乗って激辛料理などもパクパクと食べてしまった。やがて台北から帰国の飛行機に乗った筆者の、腸の具合がおかしくなり始めたのは、羽田からのモノレールが浜松町に着いた頃だったかな。そこから、当時住んでた千葉県の柏市に電車で帰り着くまで、筆者がどれほどの艱難辛苦を耐え忍んだことか…。なにしろヤバかったのだ。そこから得た教訓は、激辛料理は食べるときは美味いが、後がちと怖いということ。
ちなみに、唐辛子の辛味成分として知られるのがカプサイシン。ある学者の研究によれば、人が唐辛子を食べて頭痛・腹痛・下痢などの症状を起こすのは、体がカプサイシンの刺激を火傷と間違えたことによる反応だとか。なるほどね、そうだったのか。まあたしかに唐辛子のピリッと来る感じは、火傷の瞬間のアチッという感覚と似ているものな。なので胃腸のことを考えるなら、カプサイシンの大量摂取は控えた方が良さそうだ。ただし少量のカプサイシンは適度に胃を刺激し、胃液や唾液の分泌を活性化させ、食欲を増進させてくれる。やはり筆者などは焼き鳥やうどんに、少しだけ一味唐辛子をかける程度にしておこう。
もっとも、日本人も慣れれば激辛料理に耐性が出来る。辛いカレーも毎日食べていれば、辛さを感じなくなるというわけだ。今では街に、激辛が売り物のラーメン屋やカレー屋は珍しくなく、またタイ料理店や韓国料理店、中国料理店などに入れば、激辛のうまい料理がいつでも食べられる。しかもそうした店はけっこう人気があるのだ。辛いものが苦手だった日本人も、すっかり味覚が変化し、胃腸が丈夫になったということだろうか。そういや東京には、ありとあらゆる外国料理の店がある。日本人の味覚への貪欲さは、底がないのかもしれないなあ。
こうした辛い料理が生まれる要因は、いくつかあるのだろう。一つはやっぱり暑い国々のように、肉や魚の腐敗防止や臭い消しのため、香辛料が必要だったことが考えられる。もう一方で寒い国では、血行を良くし体を中から温めるため、香辛料を活用した料理が生まれたのだろう。前者の代表がインドやタイのカレー料理なら、後者の代表は韓国のキムチチゲかな。なので、気候が温暖で新鮮な海の幸や山の幸が豊富に手に入る日本には、辛い料理が発達しなかったのかもしれないね。まあ、生魚料理に付き物のワサビや、九州から生まれた柚子胡椒、新潟県のかんずりなどもあることはあるが、これらは料理の薬味にすぎないものな。
ところで、唐辛子の入った辛い料理を食べると、つい水を飲みたくなるが、これはどうやら逆効果らしい。辛味成分のカプサイシンは水には溶けず、かえって口の中に広がってしまうのだとか。効果があるのは牛乳やヨーグルトなどの乳製品で、カプサイシンを溶かして口の中から流してくれるそうだ。他にも砂糖や油脂を使ったデザートは、辛さをマイルドにしてくれるのだという。そう言えば中国料理店の辛い麻婆豆腐を食べた後は、デザートの杏仁豆腐がバカ美味いし、タイ料理の最後にはタピオカの入った甘いココナツミルクが食べたくなる。なるほど、世の中はうまく出来ている。やっぱりデザートは、必要から生まれたものだったのだな。
2022年03月31日
『紅い花』の季節に思う

いよいよ桜が咲いて春爛漫という季節になった。金のかからない散歩が趣味の筆者だが、この季節は歩きながら花見が出来るのが嬉しい。筆者にとって春の散歩は、メタボ対策でありまた目の保養でもある。つまり一石二鳥というやつだ。だが百花繚乱というように、この季節は桜以外にも様々な花が咲いている。中でも筆者が気になるのが、ヤブの中に真紅の花を咲かせる椿なのだ。椿の紅い色は、本当に深い色なんだよな。
筆者が椿の花の色に惹かれるのは、たぶんある名作マンガにイメージが重なるからだろう。そのマンガとは、つげ義春の『紅い花』だ。筆者がこのマンガと出会ったのは、ずいぶんむかしのことだが、まるで映画のような場面構成と物語の深い叙情性に、衝撃を受けたのを覚えている。マンガでここまで表現出来るのか、という驚きは新鮮だったね。そのクライマックスシーンに登場する紅い花は、マンガでは名前は伏せてあるものの、どう見ても椿なのだ。
モノクロのマンガなのでむろん色はついてないが、その花の色は黒ベタで表現してある。黒は真紅の花の色を連想させる。しかも、重たげな首がとれてポタリと水面に落ちる様は、椿そのものと言っていいだろう。ところがこの物語の設定は、陽光まぶしくセミの鳴く真夏になっている。つまり少年と少女の、真夏の初恋物語のシンボルが、冬から春に花を咲かせる真紅の椿というわけだ。筆者はここに作者であるつげ義春の、自由なイメージの広がりを感じるんだよなあ。
そういえば、筆者が同氏の『長八の宿』というマンガに旅心をくすぐられ、舞台である西伊豆の松崎を訪ねたのも、ずいぶん前のことだった。これは旅をする主人公が、松崎の「長八の宿」という古い旅館に泊まり、そこに住むジッさんという下男と心の交流をするという物語。まるで短編小説を読むような、作者の豊かな才能を感じさせる作品だが、ラストシーンでは別れを迎えた二人の前に、駿河湾越しに巨大な富士山が姿を見せるのが印象的だった。マンガでは最後の1ページをまるまる、ドーンと富士山のシルエットが占めていたっけ。
そこで筆者も同じ体験をしてみようと、西伊豆の海岸線沿いの道路を路線バスで南下したというわけ。その日は天気も好く、初めのうち車窓からは富士山の美しい姿が、海の向こうにはっきりと見えていた。ところがバスが南に下るにつれ、富士山はどんどん小さくなる。そして土肥を過ぎ堂ヶ島を過ぎ、ついに松崎に着いた頃には、霞の向こうに消えてしまっていたのだった。つまり、マンガで描かれたような巨大な富士山のシルエットは、作者のまったくの虚構だったわけだ。なあんだと筆者はそのとき思ったが、考えてみればそれもまた作者の自由な想像力の産物。創作とはこういうものかと、教えられたのだった。
しかし今あらためて、本棚からつげ義春の作品集を引っ張り出してみると、1960年代後半から70年代前半にかけての氏の仕事は、珠玉作品のオンパレードだ。『海辺の叙景』や『紅い花』『ほんやら洞のべんさん』といった叙情性あふれるものから、『山椒魚』『ねじ式』『ゲンセンカン主人』のようなシュールなものまで、どれも作家の才能があふれ出た、きらめくような作品ばかり。つげ義春は、マンガの新たな世界を切り拓いた開拓者なのだ。この人の本当にスゴいところは、画力も素晴らしい(若いときに限る)が、ストーリーテラーとしても非凡なところだろう。
そんな筆者が驚いたのは、ついこの2月のこと。なんとそのつげ義春氏が、日本芸術院の会員に選出されたというニュースが目に入ったのだ。ええっ、ホンマかいな? 日本芸術院といえば、わが国の優れた芸術家を顕彰する文化庁の機関。その会員には美術や文芸・音楽・演劇など、斯界の巨匠ともいうべき錚々たる人物が名を連ねている。とてもマンガ家などが入り込む隙間のない、ハイソな世界だと筆者は思っていた。ましてつげ義春といえば知る人ぞ知る、世の中の底辺を生きるビンボー作家という印象が強い。この選出には、誰だって驚いたんじゃなかろうか。
もっとも、長年のファンである筆者にとって、これは嬉しいニュース。なにしろ、ようやく氏の作品に日が当たり、高い芸術性が国にも認められたわけだ。まるで泥の中に眠っていた古代ハスの種が、一気に花を咲かせたようなものじゃないか。これはマンガの地位向上にもつながる話だし、氏の名作の数々はもっと多くの人に読まれるべきだと思う。ニュース画像で見た最近のつげ氏は、すっかり白髪のおバアさんのような風貌になっていたが、まだまだお元気そうだった。人生の最晩年に栄誉を手に入れた氏には、今後もさらに長生きをしてほしいね。
2022年02月28日
ワクワクさせる鎌倉殿

今年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が面白い。小栗旬演じる北条義時を主人公にした、鎌倉幕府草創期の人間模様を描いたドラマで、筆者は毎回楽しみに観ている。脚本は『新選組!』『真田丸』につぐ3作目の三谷幸喜。筆者はこの三谷氏のひねりの利いたストーリー作りと、ユーモアのセンスが大好きなのだ。いつの回だったか、蹴鞠が得意だという源頼朝が妻となる政子の前で、プロサッカー選手並みのリフティングを見せたときは、思わず爆笑してしまったね。いや~、驚いた。
キャスティングも超豪華版だ。主演の小栗旬をはじめ、源頼朝に大泉洋、その最初の妻に新垣結衣、源義経に菅田将暉、後白河法皇に西田敏行、平清盛に松平健など人気俳優が目白押し。また、義時の兄・北条宗時に片岡愛之助、父・時政に坂東彌十郎、僧・文覚には市川猿之助と、歌舞伎界の名優たちも顔を揃えている。やはりテレビ時代劇に歌舞伎役者が登場すると、画面がビシッと締まるような気がするな。他にも今後、大物俳優が続々出演する予定のようで、これでもかと言うほど贅沢なドラマになりそうだ。
問題は、これほど豪華で多彩な出演者が織りなすドラマに、視聴者がついて行けるかどうかだろう。なにしろ『鎌倉殿の13人』なのだ。つまり主要な登場人物がかなり多い。源平合戦の大まかな経緯や、その後の平家の滅亡までなら、普通の日本人はそれなりの知識を持っている。なにしろ日本史上の有名な話だから。だが、それから後の鎌倉幕府の権力争いが、今後のこのドラマの本筋になって行くはずだ。つまり『鎌倉殿の13人』とは、源頼朝亡き後に設けられた、13人の有力御家人による合議制を指している。たぶん、ここから陰謀渦巻くドロドロした話になるのだろうが、そもそも合議制はモメる元だもんな。
実はだいぶ前、たまたま読んだのが永井路子著『炎環』という小説。本当にたまたまだったのだが、この小説を読んだことが筆者にとって、『鎌倉殿の13人』の良い予習になっている。というのも、この4部作の小説のそれぞれの主人公が、頼朝の弟・阿野全成、有力御家人・梶原景時、政子の妹・保子、そして北条義時の4人なのだ。まさに、このテレビドラマとぴったり重なるわけ。4つの作品はそれぞれ関連しあいながら、全体として幕府の人間くさい内幕を描いた、一つの作品になっている。しかし、永井先生の女性らしい細かな表現力は、ぞっとするほどだ。
阿野全成は幼名を今若といい、あの牛若の源義経の同母兄なのだが、頼朝の下でうまく世渡りし幕府の要人になる人物。梶原景時は義経ファンにとっては悪役で知られる、鎌倉幕府の有力御家人の一人だ。むろん13人のメンバーに入っているが、小説では悲劇の武将として描かれている。政子の妹・保子は全成の妻となる女性で、姉の子(後の将軍・実朝)の乳母となり、したたかに生きる影の女だ。そして北条義時は、頼りになる兄・宗時を失った後、北条家の惣領として徐々に成長し、ついには日本全土を治める武家政権のトップに立つ男…。こんなワクワクする展開が、これからドラマの方で見られると思うと、筆者はいまから楽しみなのだ。
それにしてもこれほど登場人物が多彩だと、ドラマの脚本家も、それぞれの人物造形に頭を悩ますはず。三谷氏は多少デフォルメしながら、そこをうまく描き分けている。たとえばおっとりした源頼朝は、ときにハッタリをかます肚のすわった人物で、生真面目で野心のない義時は、今後の伸びしろの大きさを感じさせる。また時政はコテコテの田舎武士でとぼけた味が魅力だし、大柄で目ヂカラの強い政子は将来の尼将軍の素質十分だ。なにより、西田敏行演じる後白河法皇の、妖しげで人が好さそうでワルそうな雰囲気が、視聴者の興味を否応なくかきたてる。こんな法皇様はこれまで無かったよなあ。
今年の大河ドラマがワクワクさせるのは、やはり昨年の『青天を衝け』が近現代もので、シリアスドラマだったせいもあるのだろう。話はなにしろ、幕臣から実業家になった渋沢栄一の一代記。そもそも地味な人物だし、時代が現代に近いぶん残された資料なども豊富だ。そこに話を膨らませる大胆な虚構や、脚本家の想像力を差し込むスキマなどは、ほとんどなかったに違いない。そんな真面目でやや堅苦しいドラマに、一年間付き合った視聴者は、やはり次は戦いと陰謀うごめく歴史モノを、と願っていたことだろう。
鎌倉時代はそのリクエストに応えるには、最適の舞台と言えそうだ。『吾妻鏡』や公家の日記など歴史資料はあるにせよ、そこにはない隠された部分も多いはず。つまり脚本家が想像力を駆使し、存分に腕を振るえる余地がいくらでもあるということだ。物語の作り手としては、魅力に満ちた時代じゃないのかな。前作が近代資本主義のお勉強の時間だったのに比べ、この『鎌倉殿の13人』は視聴者が肩の力を抜いて楽しめる、歴史エンタテインメントとして期待できる。筆者も御家人たちの陰惨な潰しあいを、三谷氏がどう明るく料理してくれるか楽しみにしたい。








