2025年01月31日
本が大好き、江戸時代
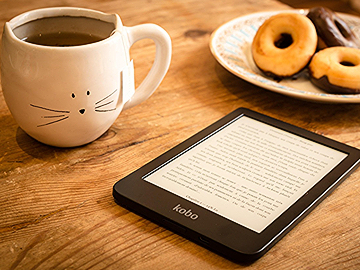
NHKの今年の大河ドラマ、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』が1月5日から始まったが、今のところ筆者の期待通りなかなか面白い。なにしろ舞台は、これまでの大河で描かれなかった江戸時代の吉原遊廓。しかも、主人公やそれを取り巻く連中は、いわば風俗業で生きている町人たちだ。吉原に暮らす女郎たちの実態や、その哀れな陰の部分もちゃんと描かれており、斬新といえば斬新なドラマになっている。初回でいきなり、遺棄された4人の女郎の全裸死体が出てきたときには、さすがの筆者もギョギョッ!とわが目を疑ったけど。
しかし昨年の『光る君へ』が、平安時代の優雅な王朝モノだったのに比べ、今回はのちに江戸の出版王となる蔦屋重三郎の出世物語なのだから、NHKもずいぶん大胆なシフトチェンジをしたもんだ。ここは筆者も大いに評価したい。なんたって手垢のついた戦国モノや幕末モノは、もう視聴者も飽き飽きしている(にもかかわらず、来年はまた『豊臣兄弟!』てのをやるらしいが…)。なので今回の『べらぼう』では、われわれの知らない江戸時代中期の町人文化を、ぜひ深掘りして見せてほしいね。視聴者はつねに新しいものを求めている!
そんな『べらぼう』では、これまで筆者が観て印象に残ったシーンがいくつかあった。女郎の全裸死体もその一つだが、実はちょっと驚いたのが、貸本屋を営む重三郎が遊廓の女郎たちに、持ってきた本を見せていたシーンだ。女郎たちはそれぞれ好きな本を開いて見入っていたが、注目すべきは彼女たちがみな文字を読めていたこと。女郎といえば金のため親から遊廓に売られた、いわば底辺階級の女性たちだ。それなのに、いくら草双紙とはいえ人並みに読書をするのだから、さすがと言うかへえ?と言うか、筆者もちと感心させられたってわけ。
調べてみるとどうやら、吉原の遊女というのはほぼ全員が読み書きが出来たらしい。意外な事実だが、それには理由があったのだ。というのも風俗嬢の彼女らにとって、いちばん大事なのは贔屓にしてくれるお客。サービスするのはもちろんだが、お客にはリピーターになってもらわなければ困る。そこで必要になるのが、また来てねというラブレターだ。美しい字のそんな手紙を貰ったら、男だって悪い気はしないし、また行こうかなという気にもなる(バカだなあ)。なので、彼女らは遊廓に入ったときから、せっせと読み書きを勉強していたというわけ。美人で読み書きそろばんが出来る女性は、商人に身請けされて妻になるケースもあったという。
そもそも、江戸時代というのは庶民レベルでも、識字率はそうとう高かったようだ。同時代のイギリスやフランスなどの識字率が30パーセント以下だったのに比べ、江戸時代の日本では60パーセントを超えていたという説もある。まあ、正確な統計などない時代だし、都会と地方では格差もあったはずだから、真偽のほどは不明だとしても、当時の日本が読書大国だったことは間違いない事実だろう。なにしろ、武士階級なら子供の頃から藩校で勉強をしているし、町人や農民の子はあちこちにある寺子屋で読み書きを習っている。勉強好きは日本人の伝統だったのだ。
なので、江戸時代の日本が読書大国になったのは、当然といえば当然だったのだろう。元禄期(1688〜1704)は京・大坂の上方が出版業の中心だったようだが、やがて宝暦~天明期(1751〜1789)の田沼意次の時代に、江戸の出版業界が活況を呈するようになる。ここに、蔦屋重三郎が登場するというわけだ。ドラマでは貸本屋をやっていた重三郎だが、当時の貸本はとても人気があったという。なにしろ本を買うより安いし、デリバリーはしてくれるし、読む方にとって便利なことこの上ない。遊廓や商家はもちろんのこと、貸本屋は大名屋敷などにも出入りしていたらしい。そこには参勤交代で田舎から出て来た武士が、ヒマを持て余してゴロゴロしていたからね。江戸の最新刊が読めるとなれば、彼らも大喜びだったはずだ。
それにしても、当時の人々はどんな本を読んでいたのだろうか? 寛永4年(1627)に吉田光由が著してロングセラーになったのが、意外や『塵劫記』という算術についての解説書。このあたりが江戸文化の面白いところだ。また、著名作家としては井原西鶴の『好色一代男』が天和2年(1682)、『日本永代蔵』が貞享5年(1688)に出ている。貝原益軒の健康ガイドブック『養生訓』は正徳2年(1712)。蔦屋重三郎が生きた18世紀後半になると、かの『ターヘル・アナトミア』の翻訳本『解体新書』が安永3年(1774)に、上田秋成の小説『雨月物語』が安永5年(1776)に刊行されている。
重三郎自身が関わった作家で、有名人といえばまず山東京伝だろうか。二人はタッグを組んで数々のベストセラーを出したが、田沼意次に代わって幕府の老中になった、堅物・松平定信の「寛政の改革(1787〜1793」により、厳しい制限や処罰を受けた。当時は「言論・表現の自由」なんて言えなかったからなあ。だが、重三郎が育てた作家たちはのちに才能を開花させ、寛政9年(1797)の彼の死後、十返舎一九が書いた『東海道中膝栗毛』が、享和2年(1802)から出版されて大ベストセラーに。曲亭馬琴が心血を注いだ『南総里見八犬伝』は、文化11年(1814)から28年をかけて刊行され、江戸文学を代表する作品となった。こうしてみるとこの時代には、庶民向けの草双紙や物語を読ませる小説から、マニア向けの研究書まで、実にさまざまな本が読まれていたんだな。
この記事へのコメント
近年の大河ドラマは何の因果か一年おきに視聴しています。「べらぼう」についてのブログ拝読、お気に入りの様子で何よりです。自分は昨年の「光る君へ」をくだらないと思いながら辛抱強く見ました。平安時代の西暦千年頃は、王朝日記文学が盛んで、栄華物語など藤原道長のことは詳しく解るのに、脚本家が消化しきれていないと思いました。源氏物語のできた背景を探るのに失敗して凡作になったと思います。それにしても紫式部、清少納言、赤染衛門、藤原道綱母など、王宮外での生活活動は本当に見えません。都の中でも物騒なのに、山賊、海賊の出没する中を遥々と大宰府まで紫式部と下僕が二人旅とはマンガにもなりませんね。
Posted by 桜田靖 at 2025年02月23日 11:27












